債権回収
支払督促とは?未払い金回収のメリット・手続きを徹底解説
支払督促は未払い債権を法的に回収する強力な手段。メリット・デメリットから申立て手続き、費用、注意点まで、専門家が分かりやすく解説します。時効中断や強制執行への流れも網羅。債権回収でお悩みの経営者・個人事業主必見の完全ガイド!

取引先からの未払い金、売掛金の滞納、貸付金の返済遅延――。
ビジネスをしていれば、誰もが一度は直面する「債権回収」の課題。
口頭や書面での催促を繰り返しても、なかなか支払いに応じてもらえない。かといって、裁判を起こすのは時間も費用もかかりそうで躊躇してしまう。
支払督促は、裁判所を介して債務者へ支払いを促す法的な手続きでありながら、比較的シンプルかつ迅速に利用できるのが特徴です。
これを活用することで、未払い債権を法的に確定させ、最終的には強制執行へと繋げる道を開くことができます。
これを読めば、支払督促が貴社の債権回収をいかに効率的かつ確実に進める強力なツールであるかがお分かりいただけるでしょう。

支払督促とは?法的な強制力を持つ債権回収手段の基本
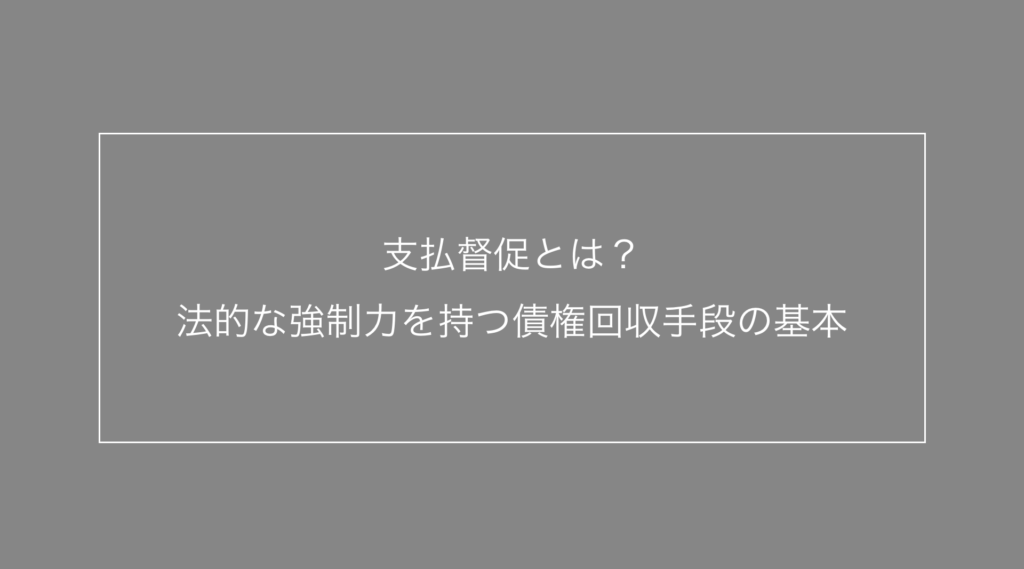
支払督促の定義と目的
支払督促とは、金銭の支払いを求める債権者(お金を請求する側)の申し立てに基づき、裁判所書記官が債務者(お金を支払う側)に対して支払いを命じる督促状を発布する手続きです。これは非訟事件手続法に基づいて行われる、裁判所を介した特別な手続きであり、通常の訴訟よりも簡易かつ迅速に進められる点が大きな特徴です。
支払督促の主な目的は以下の通りです。
- 未払い債権の法的な確定: 債務者が異議を述べなければ、支払督促は確定し、訴訟の判決と同様の法的効力(債務名義)を持ちます。これにより、将来的に強制執行(債権者の財産を差し押さえるなど)を行うことが可能になります。
- 債務者への心理的プレッシャー: 裁判所から正式な督促状が届くことで、債務者に「これは放置できない」という心理的な圧力を与え、自主的な支払いを促す効果が期待できます。
- 時効の中断(更新): 支払督促の申立ては、債権の時効を中断(改正民法では更新)させる効果があります。これにより、債権が時効によって消滅することを防げます。
支払督促の対象となる債権
支払督促の対象となるのは、金銭の支払いを目的とした債権に限られます。
具体的には以下のようなものが該当します。
ただし、金銭以外の請求(例えば、物の引き渡しやサービスの提供など)や、金額が不特定な請求には利用できません。
支払督促の手続きに関わる機関:裁判所書記官
これは、支払督促が債権者の主張だけに基づいて発せられる「書面審査」の手続きであるためです。
裁判所書記官は、申立書の内容に不備がないか、債権が支払督促の対象となる金銭債権であるかなどを確認し、問題がなければ督促状を発布します。
債務者からの異議申立てがなければ、そのまま支払督促が確定します。
支払督促と訴訟・公正証書との違い
債権回収の手段としては、支払督促の他に「訴訟」や「公正証書」も挙げられます。
それぞれの特徴と違いを理解しておくことは、状況に応じた最適な選択をする上で非常に重要です。
【支払督促・訴訟・公正証書の比較表】
| 項目 | 支払督促 | 訴訟(少額訴訟含む) | 公正証書(強制執行認諾文言付) |
| 目的 | 簡易・迅速な債務名義取得、自主的支払い促す | 権利の有無を確定、債務名義取得 | 債務内容の明確化、債務名義取得(契約時) |
| 手続き | 書面審査のみ、審尋・期日なし | 原則として口頭弁論(期日複数回) | 公証役場で作成、当事者合意が必要 |
| 費用 | 比較的安い(印紙代、郵券代) | 比較的高い(印紙代、郵券代、弁護士費用など) | 作成手数料 |
| 時間 | 比較的短い(約1~2ヶ月) | 長い(数ヶ月~数年) | 短い(合意後、即日作成も可) |
| 強制力 | 債務者が異議なしで確定すれば強制執行可 | 判決確定で強制執行可 | 公正証書自体が強制執行可(契約時に合意が必要) |
| 債務者の意見 | 異議申立てがなければ審理なし | 当事者双方の主張・証拠に基づいて審理 | 当事者間の合意に基づき作成 |
| 当事者の負担 | 比較的少ない | 比較的大きい(証拠収集、期日出席など) | 比較的少ない |
| 争点 | 債務の有無に争いがない場合に有効 | 債務の有無や内容に争いがある場合に有効 | 債務内容の明確化、将来の紛争予防 |

支払督促の6つのメリット:なぜ多くの企業・個人が選ぶのか
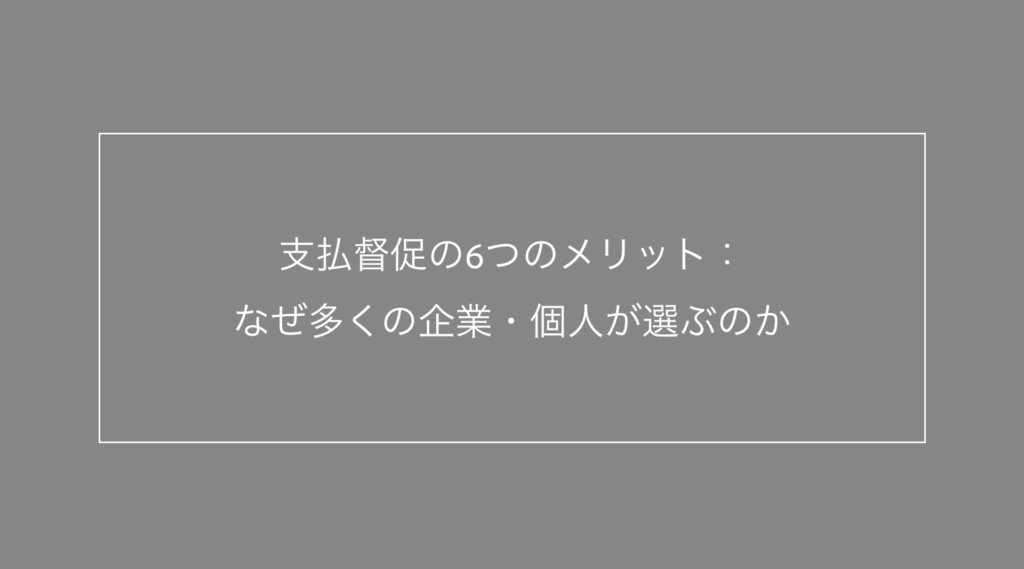
支払督促が多くの企業や個人事業主に選ばれるのには、明確な理由があります。
ここでは、その主要なメリットを6つご紹介します。
1. 裁判所を介した法的な手続きであることの強制力と信頼性
支払督促は、単なる内容証明郵便や電話での催促とは異なり、裁判所が発する法的な文書です。
この「裁判所」という権威ある機関が関与することで、債務者に対して以下のような強い心理的プレッシャーを与えることができます。
- 無視できないという意識: 「まさか本当に裁判所から書類が来るとは思わなかった」と感じさせ、自主的な支払いを促します。
- 真剣な対応を促す: 債権者が本気で回収に乗り出していることを明確に伝え、これ以上の放置はできないと認識させます。
- 信頼性の向上: 債権者が法的な手続きを踏んでいることで、債務者に対しても誠実な対応を求める信頼性のあるメッセージとなります。
2. 費用が比較的安価であること
訴訟手続きと比較して、支払督促は費用を大幅に抑えることができます。
- 印紙代: 訴訟の場合の半額です。請求額に応じて費用が変動しますが、少額訴訟よりは安価で、高額債権の場合でも費用対効果が高いです。
- 郵券代(郵便費用): 申立書類の送付や督促状の送達にかかる実費です。
- 弁護士費用の節約: 支払督促は書面審査が基本であり、手続きも比較的シンプルであるため、債権者自身で申し立てることも可能です。これにより、弁護士に依頼した場合にかかる多額の費用を節約できます。もちろん、不安な場合は弁護士に相談・依頼することも可能です。
3. 短期間で手続きを完了できる可能性
- 迅速な手続き: 申立てから支払督促の確定まで、早ければ1ヶ月から2ヶ月程度で完了するケースもあります(債務者が異議を述べない場合)。
- 時間的コストの削減: 裁判所に出廷する必要がないため、経営者や担当者が本業から離れる時間を最小限に抑えられます。
急を要する債権回収において、このスピード感は非常に重要な要素となります。
4. 債務者の住所地を管轄する裁判所で手続きできる
支払督促は、原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てます。
債権者にとっては、債務者の所在地を特定し、その管轄裁判所を確認する手間はありますが、その後の訴訟移行を考慮すると、合理的な管轄設定と言えます。
5. 債務者が異議を出さなければ強制執行が可能になる
支払督促の最大のメリットの一つは、債務者が期間内に異議申立てを行わない場合、支払督促が確定し、強制執行の申し立てが可能となる点です。
確定した支払督促は、訴訟の判決と同様に債務名義としての効力を持ちます。
- 強制執行: 債務名義があれば、債務者の財産(預貯金、不動産、給与債権など)を差し押さえるなど、法的な強制力をもって債権を回収することができます。
- 「仮執行宣言付き支払督促」: 債務者が督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てず、かつ債権者が「仮執行宣言の申立て」をすれば、支払督促は「仮執行宣言付き支払督促」として確定し、すぐに強制執行が可能になります。さらに2週間異議がなければ、完全な確定となります。
6. 債権の時効中断(更新)効果がある
民法で定められている債権の消滅時効は、一定期間行使しないと債権が消滅してしまうというものです。
支払督促を申し立てることで、この時効の進行を中断(現在の民法では「更新」と表現)させる効果があります。
- 時効の進行停止: 支払督促の申立てにより、時効の進行が一旦停止します。
- 時効の更新: 支払督促が確定した場合、または異議申立てにより訴訟に移行し、判決が確定した場合には、その時点から新たに時効が進行し始めます。これにより、債権が時効によって消滅するのを防ぐことができます。

支払督促のデメリットと注意点:失敗しないためのリスク理解
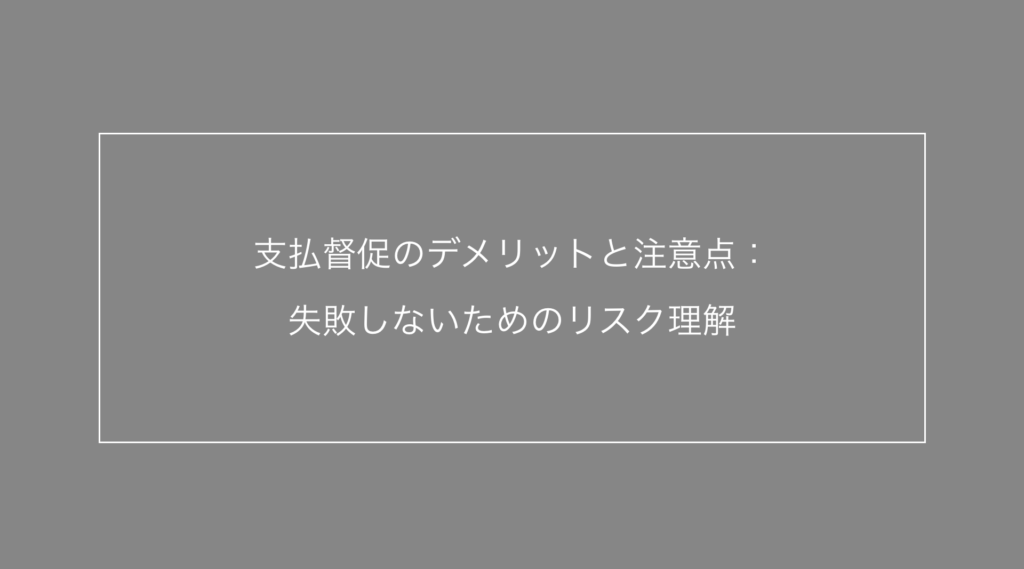
支払督促は非常に強力で有効な手段ですが、利用する際にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。
これらを事前に理解しておくことで、無駄な手間や費用を避け、より賢く手続きを進めることができます。
1. 債務者が異議を申し立てると訴訟に移行する
支払督促の最大のデメリットは、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てた場合、自動的に通常の訴訟手続きに移行する点です。
- 訴訟への移行: 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所、または請求額に応じて地方裁判所に事件が移送され、通常の民事訴訟として審理が開始されます。
- 時間と費用の増大: 訴訟に移行すると、口頭弁論の期日が複数回設定され、審理が長期化する可能性があります。また、訴訟印紙代や弁護士費用も支払督促単独の場合よりも高額になる傾向があります。
- 証拠の準備: 訴訟では、債権の存在や金額を証明するための証拠(契約書、請求書、領収書、メールのやり取りなど)を提出し、双方の主張を立証する必要があります。
2. 債務者の住所が不明だと手続きができない
支払督促は、裁判所書記官が債務者に対して督促状を送達することで手続きが開始されます。
そのため、債務者の正確な住所が不明な場合は、支払督促の手続きを進めることができません。
- 公示送達は不可: 支払督促では、債務者の住所が不明な場合に利用できる「公示送達」の手続きは認められていません。
3. 債権の存在や金額に争いがある場合は不向き
支払督促は、書面審査のみで行われるため、債権の存在や金額について債務者との間で争いがある場合には適していません。
債務者が債務内容に異議を申し立てれば、前述の通り訴訟に移行してしまいます。
4. 債務者に財産がなければ回収できない
支払督促が確定し、強制執行が可能になったとしても、債務者に差し押さえるべき財産がなければ、実際に債権を回収することはできません。
- 「絵に描いた餅」になる可能性: 債務名義は得られても、債務者が無資産状態であれば、時間と費用をかけても徒労に終わる可能性があります。
5. 債務者の心情を悪化させる可能性
裁判所からの督促状が届くことで、債務者の心情が逆なでされ、感情的な反発を招く可能性があります。
- 関係性の悪化: 特に継続的な取引関係にある場合、支払督促によって関係性が修復不可能なほど悪化し、今後の取引が困難になることがあります。
これらのデメリットや注意点を十分に理解し、自身の状況や債務者の特性を考慮した上で、支払督促を利用するかどうかを判断することが、債権回収を成功させるための重要なステップとなります。

支払督促の具体的な手続きの流れ:申立てから強制執行まで
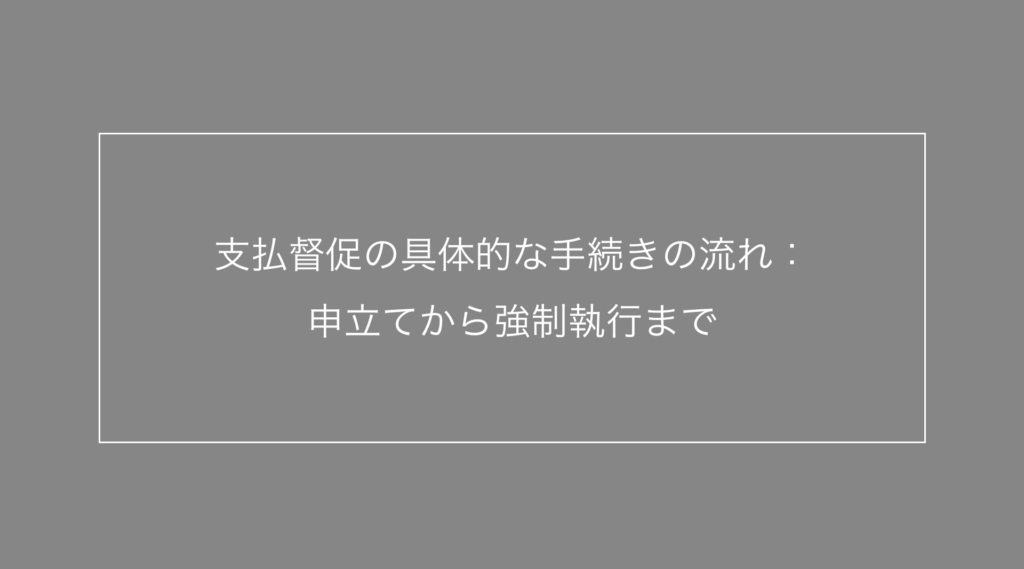
支払督促の手続きは、債権者自身で行うことも可能です。
ここでは、具体的な手続きの流れをステップごとに解説します。
ステップ1:申立ての準備
支払督促の申立ては、管轄の簡易裁判所書記官に対して行います。
- 管轄裁判所の確認: 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所が申立先となります。法務省のウェブサイトなどで確認できます。
- 必要書類の準備:
- 支払督促申立書: 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードするか、裁判所の窓口で入手できます。請求の趣旨、請求の原因(いつ、どのような契約で、いくら貸した・売ったかなど)を具体的に記載します。
- 当事者目録: 債権者と債務者の氏名(名称)、住所などを記載。
- 請求の趣旨及び原因: どのような金銭の支払いを求めるのか、その根拠(契約内容、発生経緯など)を具体的に記載します。
- 疎明資料(必須ではないが推奨): 契約書、請求書、領収書、振込記録、売買契約書、メールのやり取りなど、債権の存在や金額を証明する書類のコピー。申立書に添付して提出することで、裁判所書記官の判断をスムーズにする効果があります。
- 当事者関係図(任意): 複雑な関係の場合に添付。
- 添付書類(債務者が法人の場合):
- 会社の登記事項証明書: 債務者が法人の場合、代表者事項証明書や履歴事項全部証明書などの取得が必要になります。
- 費用(印紙代・郵券代)の計算:
- 印紙代: 請求額に応じて決まります。訴訟の半額です。
- 例:100万円の請求であれば印紙代は5,000円
- 請求額が100万円以下の場合は、50万円ごとに5,000円、100万円以上は100万円ごとに5,000円が加算されます。
- 郵券代: 債務者への送達費用など。裁判所によって金額が異なるため、管轄裁判所のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせましょう。通常、数千円程度です。
- 例:約3,000円~6,000円程度
- 印紙代: 請求額に応じて決まります。訴訟の半額です。
【請求額と印紙代の目安】
| 請求額 | 印紙代 |
| 10万円まで | 500円 |
| 10万円超~20万円 | 1,000円 |
| 20万円超~30万円 | 1,500円 |
| 30万円超~40万円 | 2,000円 |
| 40万円超~50万円 | 2,500円 |
| 50万円超~100万円 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円 | 10,000円 |
| 200万円超~300万円 | 15,000円 |
| 500万円超~1,000万円 | 25,000円~50,000円 |
| 1,000万円超~ | 請求額の0.5% |
ステップ2:支払督促の申立て
準備が整ったら、管轄の簡易裁判所書記官宛てに申立書と必要書類を提出します。
- 提出方法: 郵送または直接持参。
- 審査: 裁判所書記官は、申立書の内容に不備がないか、債権が支払督促の対象となる金銭債権であるかなどを審査します。不備があれば、補正を求められることがあります。
ステップ3:支払督促の発布・送達
申立てが受理されると、裁判所書記官が支払督促を発布し、債務者へ郵送で送達します。
- 債務者への送達: 支払督促は、特別送達という書留郵便で債務者に送られます。これにより、債務者がいつ受け取ったかが明確に記録されます。
- 債務者の対応期間: 債務者は、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てるかどうかを判断しなければなりません。
ステップ4:債務者の対応パターンとその後の流れ
支払督促を受け取った債務者は、以下のいずれかの対応をとります。
パターンA:債務者が異議を申し立てない場合
債務者が2週間以内に異議を申し立てなかった場合、債権者は仮執行宣言の申立てを行います。
- 仮執行宣言の申立て: 債権者が裁判所書記官に対し、「仮執行宣言の申立て」を行います。
- 仮執行宣言付き支払督促の発布・送達: 裁判所書記官が仮執行宣言を付した支払督促を発布し、債務者へ再度送達します。
- 支払督促の確定: 債務者が仮執行宣言付き支払督促を受け取ってからさらに2週間以内に異議を申し立てなかった場合、支払督促は確定します。確定した支払督促は、訴訟の判決と同様の債務名義となります。
パターンB:債務者が異議を申し立てた場合
債務者が2週間以内に異議を申し立てた場合、支払督促の手続きは終了し、通常の訴訟手続きに移行します。
- 訴訟への移行: 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所、または請求額(140万円超)に応じて地方裁判所に事件が移送され、通常の民事訴訟(一般調停や少額訴訟ではない)として審理が開始されます。
- 口頭弁論: 裁判所から口頭弁論期日の通知が届きます。債権者は裁判所に出廷し、訴訟手続きの中で主張・立証を行う必要があります。この段階で弁護士に依頼することを検討すべきでしょう。
- 判決: 双方の主張と証拠に基づいて審理が行われ、最終的に判決が下されます。判決が確定すれば、これも債務名義となります。
ステップ5:強制執行の申立て(確定した場合)
支払督促が確定した場合(パターンA)、または訴訟で判決が確定した場合(パターンB)、債務者がそれでも支払いに応じない場合は、強制執行の申立てを行うことができます。
- 強制執行申立書の提出: 債務者の財産(預貯金、不動産、給与債権など)を特定し、その財産のある場所を管轄する地方裁判所や簡易裁判所に強制執行の申立てを行います。
- 財産調査: 申立て前に可能な範囲で債務者の財産を調査しておくことが重要です。債務者に財産がなければ、強制執行はできません。
- 財産の差し押さえ・換価・配当: 裁判所が強制執行手続きを進め、債務者の財産を差し押さえ、競売などで換価し、その代金を債権者に配当します。

支払督促を成功させるための具体的なポイントと注意点
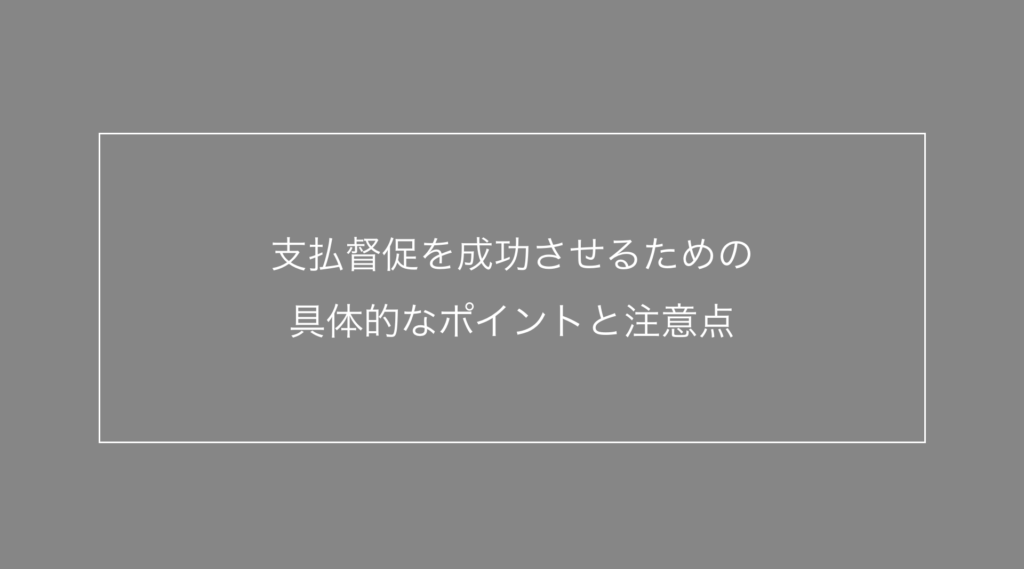
支払督促は簡易な手続きであるとはいえ、成功させるためにはいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
1. 債権の存在と金額を明確にする
支払督促の審査は書面で行われるため、提出する申立書の内容が非常に重要です。
- 客観的な根拠: 請求する金銭債権の発生原因(いつ、どのような契約で、いくらの商品やサービスを提供したか、あるいは貸し付けたかなど)を具体的に、かつ客観的に記載しましょう。
- 証拠の整理: 契約書、請求書、領収書、納品書、振込履歴、メールやチャットのやり取りなど、債権の存在と金額を証明できる資料を事前に整理し、申立書に添付することで、審査がスムーズに進みます。証拠がない、あるいは不十分な場合は、訴訟に移行した場合に不利になる可能性があります。
2. 債務者の正確な情報を把握する
債務者への送達が必須であるため、以下の情報が正確である必要があります。
- 正確な氏名・名称: 法人の場合は正式名称と代表者氏名、個人の場合は本名。
- 正確な住所: 住民票や商業登記簿謄本で確認した最新の住所。古い住所では送達ができません。
これらの情報に誤りがあると、督促状が届かず、手続きが滞ってしまいます。
3. 早めに手続きを開始する
未払い債権は、放置すればするほど回収が困難になる傾向があります。
- 時効のリスク: 債権には時効があるため、早めに法的手続きを取ることで時効の更新(中断)効果を得られます。
- 財産の散逸: 債務者の財産状況は時間とともに変化する可能性があります。早めに手続きを開始することで、債務者が財産を隠したり処分したりする前に、強制執行の準備を進めることができます。
- 交渉の機会: 督促状が届くことで、債務者との間で「一部だけでも支払う」「分割払いにする」といった交渉の余地が生まれることもあります。
4. 債務者が異議を申し立てる可能性を予測する
支払督促のデメリットでも触れた通り、債務者が異議を申し立てると訴訟に移行します。
- 債務者の性格・背景: 債務者が感情的になりやすいか、過去に同様のトラブルを起こしているか、法的な知識を持っているかなどを考慮します。
- 債権に対する認識: 債務者が債権の存在を認めているか、金額について争いがあるかなどを、これまでのやり取りから判断します。
- 訴訟への準備: 異議申立ての可能性が高いと判断される場合は、最初から訴訟を視野に入れ、弁護士への相談や証拠の整理などを早めに進めておくべきです。
5. 弁護士への相談・依頼も検討する
支払督促は、個人でも手続きが可能ですが、以下のような場合は弁護士に相談・依頼することを強く推奨します。
- 債権額が高額な場合: 失敗した場合の損失が大きい。
- 債務者との関係が複雑な場合: 感情的な対立がある、複数の債権が絡むなど。
- 債務者が異議を申し立てる可能性が高い場合: 訴訟への移行に備えて、専門家によるサポートが不可欠です。
- 債務者の財産状況が不明な場合: 弁護士は、職務上請求権を利用して戸籍や住民票の取り寄せ、あるいは弁護士会照会などを通じて財産調査の助言が可能です。
- 自分で手続きをする時間がない場合: 本業に集中するため、専門家に任せる方が効率的です。
6. 強制執行まで視野に入れる
支払督促は、最終的に強制執行に繋げるための債務名義を得る手続きです。
- 債務者の財産調査: 支払督促の申立てと並行して、債務者の財産状況(預貯金口座、不動産、勤務先、自動車など)を可能な限り調査しておきましょう。
- 優先順位の検討: 債務名義を得ても、債務者に財産がなければ絵に描いた餅です。効果的な強制執行を行うためにも、どの財産を差し押さえるべきか、優先順位を検討しておくことが重要です。

支払督促に関するよくある質問(FAQ)
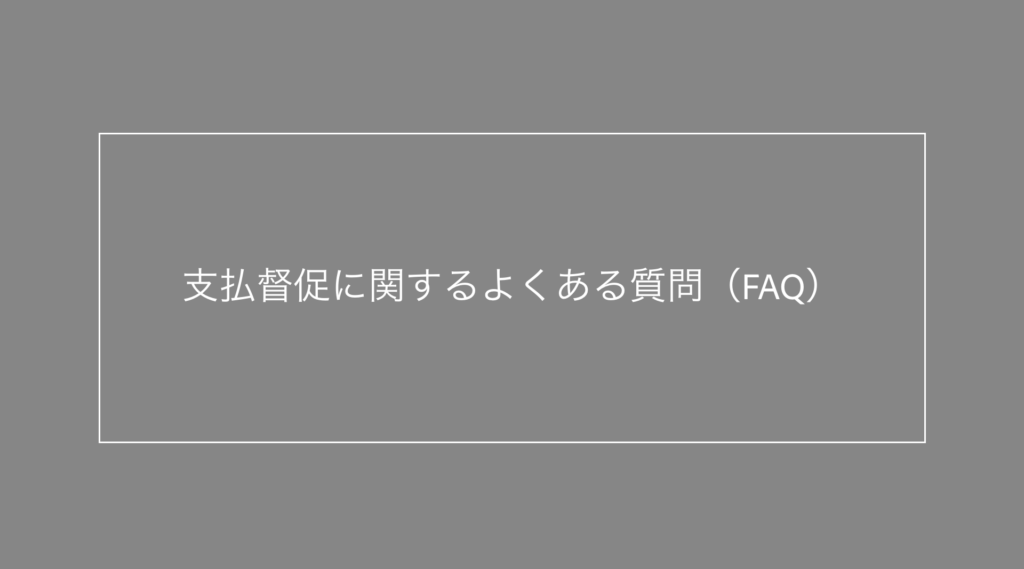
支払督促について、多くの方が抱く疑問点についてQ&A形式で解説します。
Q1:支払督促と少額訴訟、どちらが良いですか?
A1:どちらが良いかは、債権額と債務者の反応を予測して判断します。
- 支払督促が適している場合:
- 債権額に上限なし。
- 債務者が債務の存在を争わない可能性が高い場合。
- 費用を抑えたい、手続きを迅速に進めたい場合。
- 少額訴訟が適している場合:
- 請求額が60万円以下の場合のみ利用可能。
- 債務者が債務の存在を争う可能性があるが、短期間で解決したい場合。
- 原則1回の期日で審理が終了するため、比較的迅速。
債務者が異議を申し立てる可能性が高い場合は、最初から少額訴訟を検討する方が、二度手間を省ける場合があります。
Q2:支払督促は自分でできますか?
A2:はい、自分で手続きすることも可能です。裁判所のウェブサイトで申立書の書式が提供されており、記入例も公開されています。費用も印紙代と郵券代だけで済むため、弁護士に依頼するよりも安価です。ただし、記載内容に不備があったり、異議申し立てされたりした場合は、手続きが複雑になる可能性があります。自信がない場合や、金額が大きい場合は専門家への相談を検討しましょう。
Q3:相手に届かない場合はどうなりますか?
A3:支払督促は、債務者への特別送達が必須です。もし、債務者が転居している、受け取りを拒否するなどで督促状が届かない場合(不送達)、支払督促の手続きはそこで止まってしまいます。その場合、債権者は住所調査をやり直すか、支払督促を取り下げて通常の訴訟手続き(公示送達の利用も可能)に移行することになります。
Q4:債務者が異議を申し立てた場合、どうなりますか?
A4:債務者が異議を申し立てた場合、支払督促の手続きは終了し、自動的に通常の訴訟手続きに移行します。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所で審理が行われます。この段階からは、口頭弁論期日への出廷、証拠の提出、相手方の主張への反論など、通常の訴訟と同様の対応が必要になります。この段階で弁護士に依頼することを強くおすすめします。
Q5:支払督促が確定したら、すぐに差し押さえできますか?
A5:支払督促が確定すると、債務名義として強制執行が可能になります。ただし、債務名義があるからといって、債務者の財産を自動的に差し押さえられるわけではありません。債権者自身で債務者の財産を特定し、その財産に対する強制執行の申立てを裁判所に行う必要があります。預金口座や不動産、給与など、具体的な差し押さえ対象を特定する必要があります。
Q6:時効はどれくらい伸びますか?
A6:支払督促の申立てによって時効の進行は一旦停止し、支払督促が確定した時点、または異議申立てにより訴訟に移行して判決が確定した時点から、新たに時効が進行し始めます。この期間は原則として10年間です(改正民法第169条)。これにより、債権が時効によって消滅するリスクを大幅に低減できます。
Q7:自分で手続きをする際の注意点は?
A7:
- 申立書の正確な記載: 請求の趣旨、請求の原因を具体的に、かつ正確に記載することが不可欠です。金額の計算ミスや事実関係の誤りは、手続きの遅延や失敗につながります。
- 添付資料の準備: 疎明資料(契約書、請求書など)は、申立書の内容を裏付ける重要な証拠となります。コピーを添付する際には、鮮明で判読可能なものを用意しましょう。
- 裁判所書記官との連携: 不備があれば補正を求められます。裁判所書記官からの連絡には迅速かつ的確に対応しましょう。不明な点があれば、積極的に質問することも大切です。
- 郵便切手(郵券)の過不足: 郵券の金額は裁判所によって異なる場合があるので、事前に確認し、不足がないようにしましょう。

まとめ:支払督促を戦略的に活用し、債権を確実に回収しましょう!
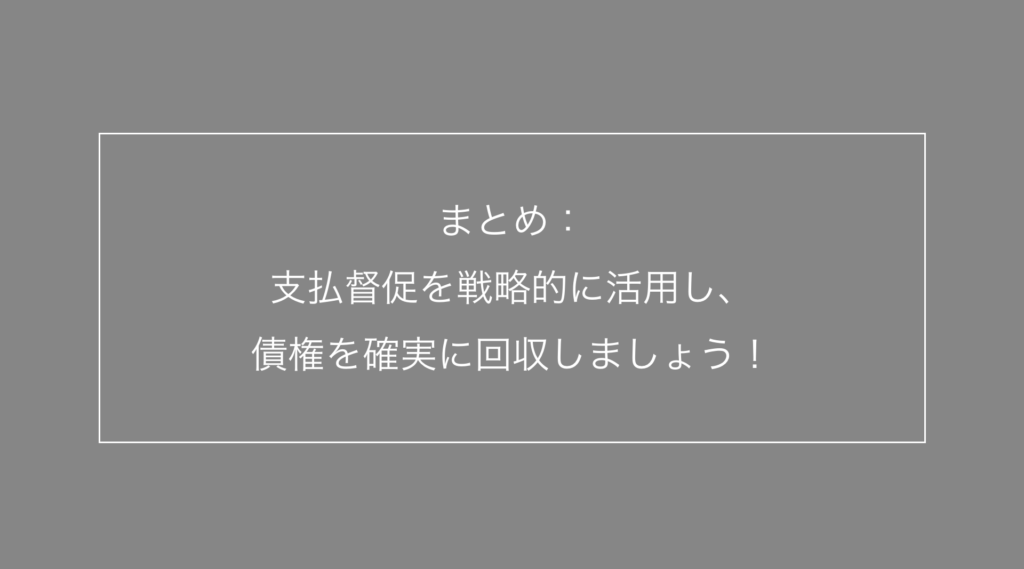
未払い金の問題は、企業の資金繰りや経営の安定を脅かす深刻な課題です。しかし、泣き寝入りする必要は一切ありません。
債務者が異議を申し立てなければ、訴訟を経ずに強制執行へと繋がる債務名義を迅速に取得できます。
また、時効の更新効果も得られるため、債権を保護する上でも重要な役割を果たします。
もちろん、債務者が異議を申し立てた場合には訴訟に移行する、債務者の住所が不明だと利用できない、といったデメリットもあります。
しかし、これらの注意点を事前に理解し、適切な準備と対応をすることで、支払督促は貴社の債権回収を成功に導く強力な武器となります。
回収できない債権は、貴社の事業を圧迫し続ける「負債」でしかありません。
【補足:成功報酬で債権回収するならXP法律事務所とは】
XP法律事務所は、債権回収を成功報酬で行います。
ご興味ある方は下記から相談

債権回収に関してご相談
FAQ
①売掛保証・債権保証とは?
売掛保証とは、企業が商品やサービスを販売した際に発生する売掛金(未回収の代金)が、取引先の倒産や支払い遅延などで回収できなくなった場合に、保証会社や保険会社がその損失を補償してくれるサービスです。
これは、債権保証とも呼ばれ、企業の資金繰り安定や貸倒れリスクの軽減を目的としています。売掛保証を導入すれば、安心して新規取引や大口契約に挑戦でき、事業拡大を後押しする効果が期待できます。いわば、会社の売上を守る「安心の保険」のようなものです。
申し込みはこちら:https://toshika-lp.protocol.ooo/protocol-deal
②債権回収・未払い回収とは?
債権回収とは、企業や個人が、商品やサービスの提供、または貸付などによって発生した「債権」(お金を受け取る権利)について、約束の期日になっても相手方(債務者)から支払いがない場合に、そのお金を取り戻すための一連の活動を指します。
具体的には、支払いの催促(督促)、交渉、そして最終的には法的手段(内容証明郵便の送付、少額訴訟、通常訴訟、強制執行など)を通じて、未回収の資金を回収するプロセスです。会社の資金繰りを健全に保つ上で非常に重要な業務です。
申し込みはこちら:https://xp-law.com/saikennkaisyuu
