債権回収
未払い金が発生したら?自社でできる初期督促と交渉のコツ
未払い金が発生したら、どうする?自社でできる初期督促と交渉の具体的なコツをプロが徹底解説。電話、メール、書面での効果的なアプローチで、費用を抑えてスムーズに未払い金を回収する方法をお伝えします。

序章:未払い金は放置厳禁!企業の「血流」を守る初期対応の重要性
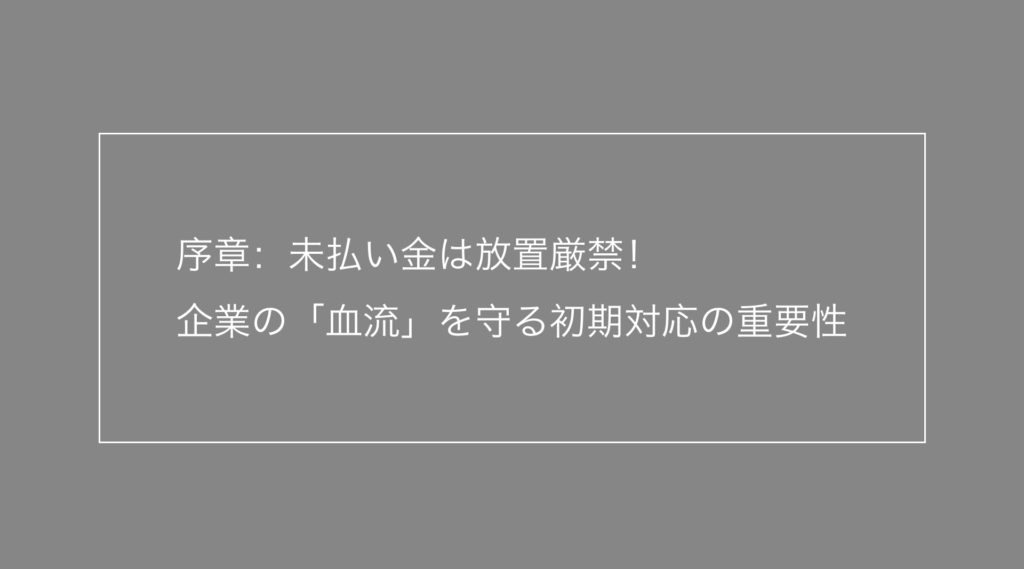
企業活動において、商品やサービスを提供し、それに対する代金(売掛金、未払い金)を受け取ることは、企業の「血流」そのものです。この血流が滞ると、企業は生命活動を維持できなくなり、最悪の場合、資金ショートや「黒字倒産」という事態に陥りかねません。
「支払期日を過ぎてしまった…どうしよう?」 「催促の電話をするのは気が引ける…」 「何度も連絡してもつながらないし、もう諦めるしかないのか…」
多くの経営者や経理担当者は、未払い金が発生した際、どのように対応すべきか悩みを抱えています。
初期段階での迅速かつ適切な対応は、未払い金を確実に回収し、企業のキャッシュフローを守る上で極めて重要です。
この記事を読み終える頃には、あなたは未払い金に対する不安から解放され、自信を持って初期対応に臨めるようになっていることでしょう。
もう未払いで悩む必要はありません。

第1章:未払い発生のメカニズム:なぜ、あなたの売掛金は未払いになったのか?
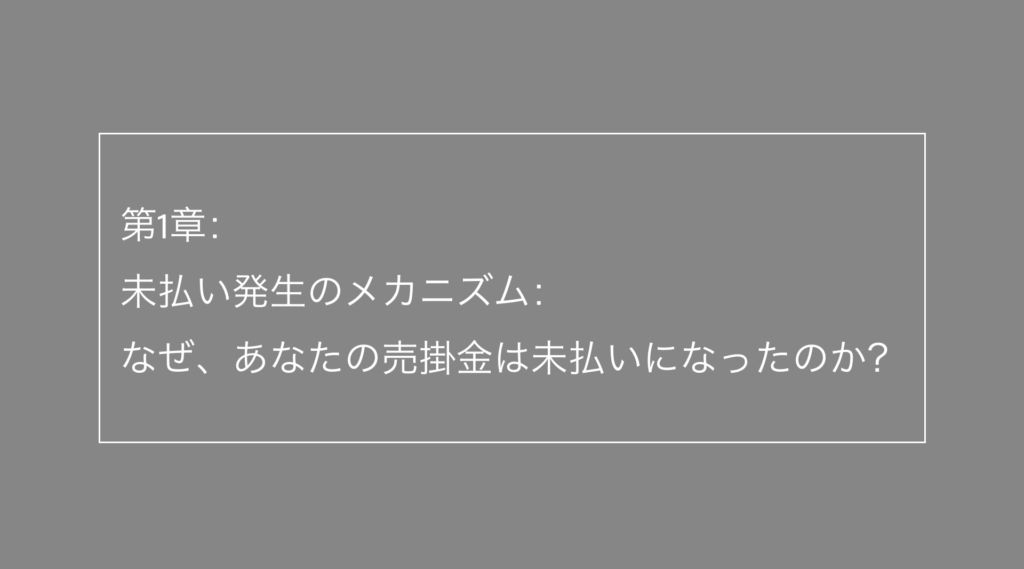
原因が分かれば、より効果的な回収戦略を立てることができ、さらには将来的な未払いを予防するための対策も講じられます。
1-1. 債務者側の要因:支払いができない、あるいはしない理由
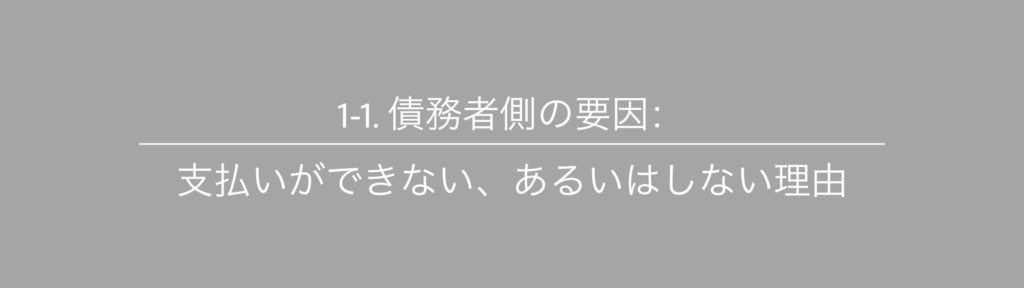
未払いの主な原因は、債務者側、つまり支払うべき取引先の状況にあります。
- 資金繰りの悪化・経営不振:
- 最も一般的な原因であり、企業活動を継続するための運転資金が不足している状態です。売上が低迷したり、大きな損失を出したり、予期せぬ出費があったりすることで、支払いに回せる現金がない状況です。
- この段階では、債務者自身も支払いたくても支払えない状況であり、督促をしてもすぐに回収できる可能性は低いです。初期督促で状況を把握し、必要であれば弁護士などの専門家への移行を検討する段階です。
- 兆候: 支払い遅延が頻繁になる、連絡がつきにくくなる、担当者が変わる、業績悪化の噂が立つ、工場や店舗が閉鎖される、主要取引先との契約が終了する、といった情報には注意が必要です。
- 倒産・破産手続:
- 債務者が法的に倒産手続き(破産、民事再生、会社更生など)に入った場合、債権回収は極めて困難になります。法的な枠組みの中で債権が処理されるため、一般債権者として回収できる金額はごくわずか、あるいはゼロになる可能性が高いです。
- 兆候: 官報公示、弁護士からの受任通知(破産申立準備の連絡)、手形不渡り情報の確認など。この段階に至る前に手を打つことが重要です。
- 悪意の支払い拒否・踏み倒し:
- 意図的に支払いを拒否するケースです。これは、最初から支払う意思がない「詐欺的行為」である場合と、支払期日を過ぎてから「品質が悪い」「納期が遅れた」などの不当なクレームをつけて支払いを拒否するケースがあります。
- 兆候: 連絡を一切無視する、内容証明郵便にも反応しない、不合理なクレームを繰り返す、所在不明になるなど。この場合は、初期督促では限界があり、法的手続きや専門家の介入が必須となります。
- 経理・事務処理上のミス:
- 意外と多いのが、債務者側の経理担当者の単純なミスや、請求書の紛失、システムエラーなどによる支払い忘れです。悪意はなく、単に処理が滞っているだけのケースです。
- 兆候: 担当者と連絡が取れればすぐに支払いが行われる、過去にも同様のミスがあったなど。この場合は、丁寧な確認と再請求で解決することがほとんどです。
- 担当者の退職・不在:
- 請求書を受け取っていた担当者が退職したり、長期不在になったりして、引き継ぎが不十分だった場合に未払いが発生することもあります。
- 兆候: 連絡先の担当者と連絡が取れない、新しい担当者が状況を把握していないなど。適切な部署や担当者に再連絡することで解決します。
1-2. 債権者側の要因:未払いを招く「見落とし」
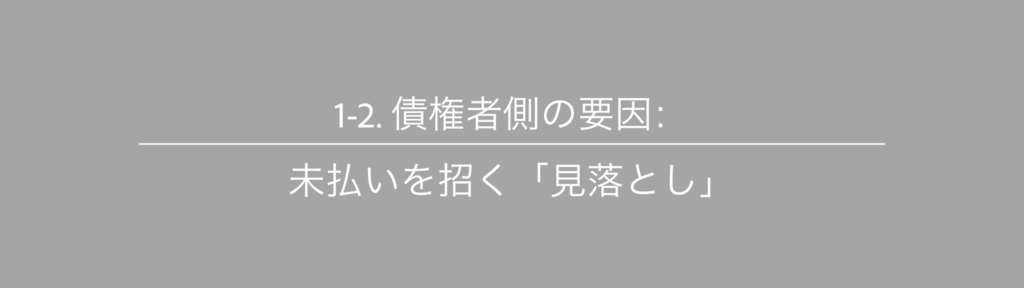
未払いは債務者側だけの問題ではありません。
- 与信管理の不徹底:
- 最も重要かつ見落とされがちな原因です。新規取引開始前に、取引先の信用力(支払い能力、過去の支払い履歴、財務状況など)を十分に調査せず、リスクの高い取引先に多額の売掛金を発生させてしまうケースです。
- 具体的な例: 設立間もない会社、資本金が極端に少ない会社、過去に支払い遅延があった会社の与信調査を怠る、大口取引の与信限度額を設定しない、与信限度額を超えて取引を継続するなど。
- 予防策: 信用調査会社の利用、インターネット上の情報収集、取引先へのヒアリング、与信管理規程の整備、与信限度額の設定と厳守。
- 債権管理の不備:
- 請求書の不備: 記載ミス、送付漏れ、送付先の誤りなどにより、請求書が正しく届かず、支払いが遅れることがあります。
- 期日管理の甘さ: 支払期日を正確に把握していなかったり、期日を過ぎてもすぐに督促に着手しなかったりすることで、回収が遅れるだけでなく、債権が時効にかかるリスクも生じます。
- 督促の遅れ・放置: 支払い遅延が発生しても、すぐに督促を行わず放置してしまうと、債務者側も「甘い会社」と認識し、支払いを後回しにする傾向が強まります。
- 証拠保全の不備: 契約書、発注書、納品書、請求書、メールや電話の記録など、取引の証拠となる書類が不十分な場合、万が一の法的手続きの際に不利になることがあります。
- 契約条件の曖昧さ:
- 口約束のみでの取引や、契約書の内容が不明確な場合、支払い条件(期日、金額、支払い方法など)や、商品・サービスの瑕疵に関する取り決めが曖昧になり、後でトラブルになる原因となります。
- 予防策: 全ての取引において書面での契約を締結し、条件を明確にする。
- 担当者の属人化:
- 債権管理が特定の担当者に依存している場合、その担当者が不在になったり退職したりすると、債権の状況が分からなくなり、回収が滞る原因となります。
- 予防策: 債権管理業務の標準化、複数人での情報共有、システム導入。
特に、初期督促はこれらの原因を早期に特定し、適切な対応に繋げるための重要なステップです。

第2章:自社でできる初期督促の鉄則:スピードと証拠保全が命
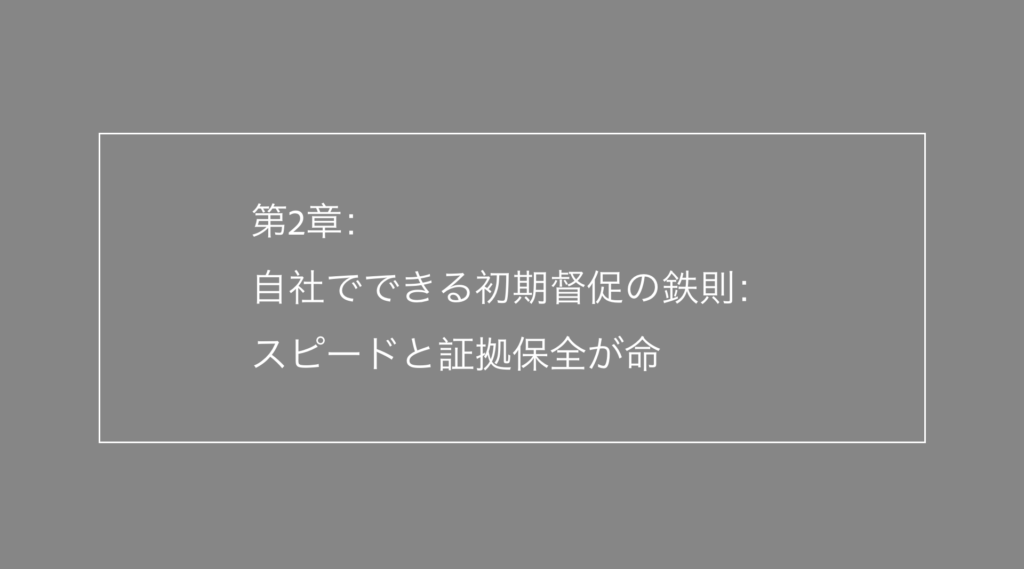
未払い金が発覚したら、何よりも「迅速な初期対応」が重要です。
ここでは、自社でできる初期督促の具体的なステップと、そのコツを解説します。
2-1. 回収前の準備:まずはここから始める!
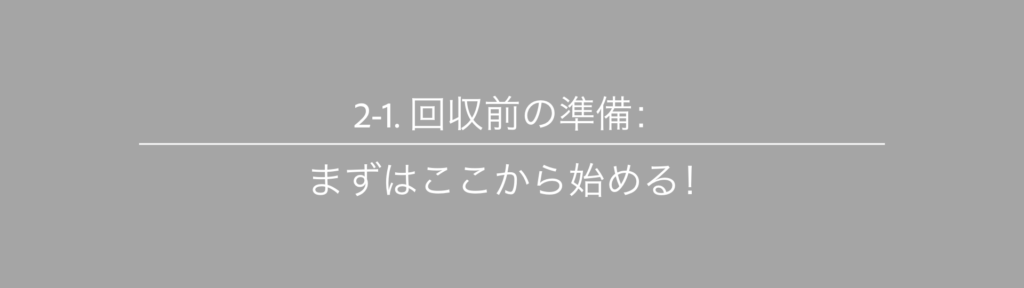
- 債権の正確な確認と証拠の整理:
- 最も重要です。未払いとなっている債権の金額、発生日、支払期日、取引内容などを正確に確認します。自社の請求書に誤りがないか(金額、口座情報、振込先名義など)も徹底的にチェックしましょう。
- 関係書類の整理: 契約書、発注書、納品書、請求書、見積書、受領書、メールやFAX、LINEのやり取り、打ち合わせ議事録、通話録音など、債権の存在と内容を証明できるあらゆる証拠を時系列で整理し、データと書面の両方で保管しましょう。口頭での約束しかなかったとしても、関連するメールのやり取りや日報など、間接的な証拠も集めておきます。
- 債務者情報の再確認とリサーチ:
- 債務者の最新の連絡先(電話番号、メールアドレス、住所、担当者名、法人であれば代表者名など)を再確認します。
- 可能であれば、債務者のウェブサイトやSNS、ニュース記事などを確認し、現在の営業状況や評判、資金繰りに関する情報を把握しておくと良いでしょう。倒産情報や風評がないか、帝国データバンクなどの信用調査会社(有料)を利用することも有効です。
- 回収方針の決定と社内連携:
- 「いつまでに」「いくら回収したいか」という目標を明確にします。
- 一括払いが難しい場合、分割払い、支払い期日の延長、一部弁済など、どのような条件なら応じられるかを事前に社内で検討しておきましょう。
- 未払い金対応は、営業、経理、法務など複数の部署が連携して行う必要があります。誰が、いつ、どのような対応をするのか、担当者間で情報共有のルールを定めておきましょう。
2-2. 初期督促の具体的な方法と交渉のコツ
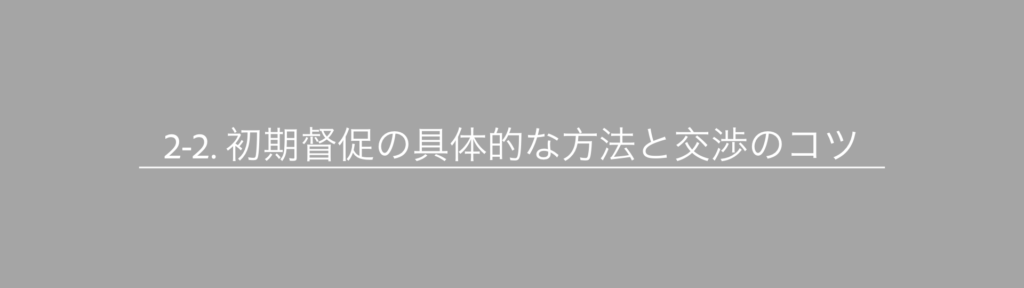
- 電話による督促(初回):最も早く、優しく、しかし確実に
- 支払期日を1日でも過ぎたら、躊躇せず、まず電話で連絡します。「支払い忘れ」や「経理ミス」の可能性もあるため、最初は丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
- 伝えるべきこと:
- 会社名、氏名、用件(未払い金の件)。
- 請求書番号、金額、支払期日、入金確認が取れていない事実を明確に伝えます。
- 「お忙しいところ恐縮ですが、お支払い状況を確認させていただけますでしょうか」など、クッション言葉を使いながら、丁寧な姿勢を示します。
- 聞くべきこと:
- 支払い状況(支払い済みか否か)。
- 未払いの具体的な理由(経理ミス、資金繰りなど)。
- 具体的な支払い予定日(いつ、いくら支払うのか)。
- 記録の徹底: 会話の日時、相手の氏名、役職、会話内容(理由、支払い約束、支払い予定日など)を必ずメモに残し、日付と共に保管します。
- ポイント:
- 冷静さを保つ: 感情的にならず、あくまで事務的に事実に基づいて話を進めます。
- 相手の状況を理解しようとする姿勢: 支払いできない理由を丁寧に聞き出し、今後の交渉材料とします。
- 曖昧な返答は許さない: 「そのうち払う」「確認します」といった曖昧な返答はせず、「具体的にいつ支払われますか?」「いつまでに確認できますか?」と明確な回答を引き出しましょう。
- メールによる督促:証拠に残る、柔軟なコミュニケーション
- 電話で連絡が取れない場合や、電話での会話内容を書面で残したい場合に有効です。メールは履歴が残るため、証拠保全にも役立ちます。
- 内容:
- 件名で内容がわかるようにする(例:「〇月分ご請求に関するご連絡(〇〇株式会社)」)。
- 電話と同様、未払いの事実と具体的な金額、期日を再確認します。
- これまでの電話やメールでのやり取りに言及し、「〇月〇日にご連絡差し上げておりますが」と経過を示すとより丁寧です。
- 支払い状況の確認と、具体的な支払い予定日の連絡を促します。
- 請求書データの再添付や、自社連絡先を明記。
- ポイント:
- 丁寧かつ明確に: 長文にならないよう簡潔にまとめ、誤解のない表現を心がけます。
- 開封確認機能の利用: 相手がメールを開封したかどうかを確認できる機能を利用することも有効です。
- 督促状・請求書再送付:書面による心理的プレッシャーの強化
- 電話やメールでの督促で進展がない場合、書面による督促に移行します。段階的にプレッシャーを高めていくことが重要です。
- 送付タイミング:
- 支払期日後1週間〜10日程度で1回目の督促状(再請求書兼)。
- 支払期日後2週間〜3週間程度で2回目の督促状(強い口調で)。
- 支払期日後1ヶ月〜2ヶ月程度で内容証明郵便を検討。
- 内容:
- 未払い債権の詳細(請求書番号、金額、支払期日、品目など)を再明記。
- これまでの督促履歴(〇月〇日の電話、メール、前回の督促状など)を簡潔に記載。
- 最終的な支払期日を設定し、「この期日までに支払いが確認できない場合は、やむを得ず法的手段を検討いたします」といった文言を明確に記載します。
- 遅延損害金が発生する場合は、その旨も明記します。
- 送付方法:
- 普通郵便: 簡易な督促。
- 特定記録郵便: 発送した事実と受け取った事実を記録できます。
- 内容証明郵便: 「誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるため、後の裁判で強力な証拠となり、債務者への心理的圧力が非常に高いです。また、**債権の時効を更新(中断)**する効果もあります(時効期間をさらに6ヶ月間延長できる)。法的手段移行を視野に入れるなら必須のステップです。
- 訪問による交渉(慎重に):対面での解決を目指す
- これまでの督促で効果がない場合、債務者の状況を直接確認し、対面で支払い交渉を行います。
- ポイント:
- 事前にアポイントを取り、複数人で訪問する(安全確保と客観的証拠のため)。
- 債務者の現状をヒアリングし、支払い能力の有無、支払い意思を確認する。
- 具体的な支払い計画(分割払い、期日延期、一部弁済など)を提案し、合意形成を目指す。
- 合意した内容は必ず書面で残す(念書、覚書など)。公正証書にすることも検討。
- 注意点:
- 債務者が感情的になったり、暴力的な言動があったりする場合は、直ちに引き揚げ、警察への相談も検討する。
- 債務者の施設や敷地内で大声を出す、居座るなどの行為は、不退去罪や強要罪に問われる可能性があるため、絶対に行わない。冷静かつ合法的な範囲で対応しましょう。
2-3. 自社督促・交渉の成功鉄則まとめ
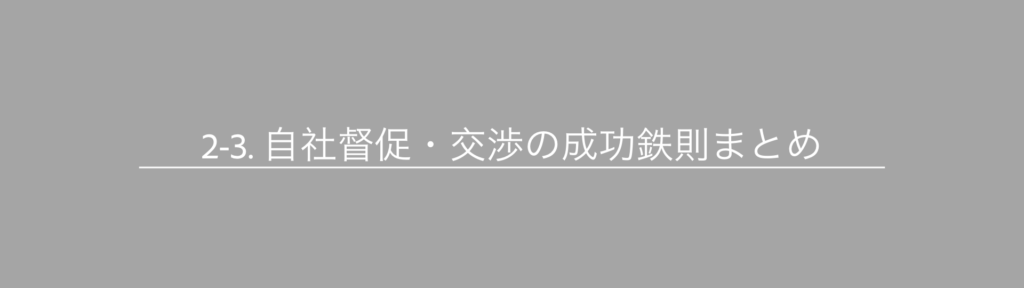

第3章:交渉が決裂したら?法的手段を視野に入れた対応
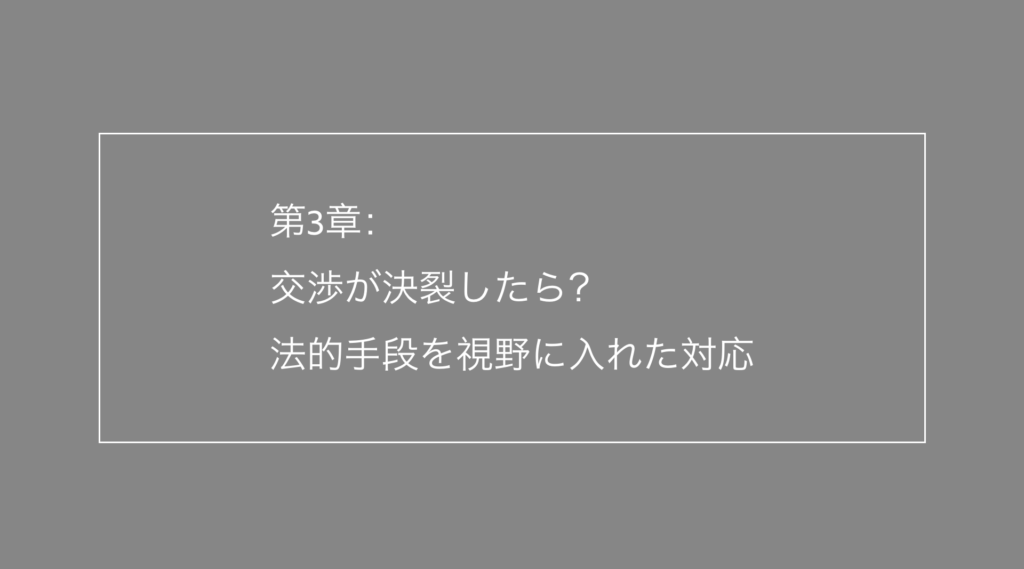
自社での督促や交渉で回収が困難な場合、法的手段を視野に入れた対応に移行する必要があります。
3-1. 法的手段への移行を見据えた準備
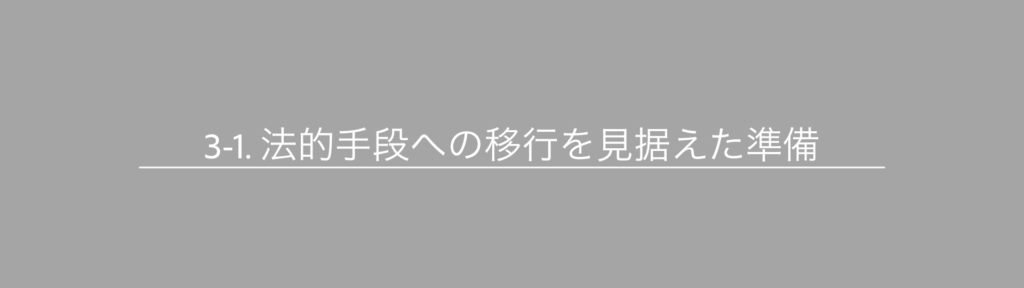
- 債権の証拠を再確認・整理:
- 法的手続きに進むには、債権の存在と内容を客観的に証明できる確固たる証拠が必要です。
- これまでに集めた契約書、請求書、納品書、メール、通話記録、交渉記録などを改めて整理し、不足がないか確認しましょう。
- 債務者の財産状況の調査(可能な範囲で):
- 法的手続きで債務名義(強制執行の根拠となる公的な文書)を得たとしても、債務者に財産がなければ強制執行はできません。
- 公開情報(法人登記情報、不動産登記情報など)や、信用調査会社の情報、業界の噂などを参考に、債務者に回収可能な財産があるかどうかを可能な範囲でリサーチしておきましょう。
- 専門家への相談を検討:
- この段階で、弁護士や司法書士といった専門家に相談することを強く推奨します。
- 専門家は、債権回収に関する法的知識と経験が豊富であり、自社での回収が難しい案件でも、法的な手続きを通じて回収の可能性を高めてくれます。
- 初回無料相談などを活用し、まずは専門家からアドバイスを受けてみましょう。
3-2. 少額債権にも有効な法的手段
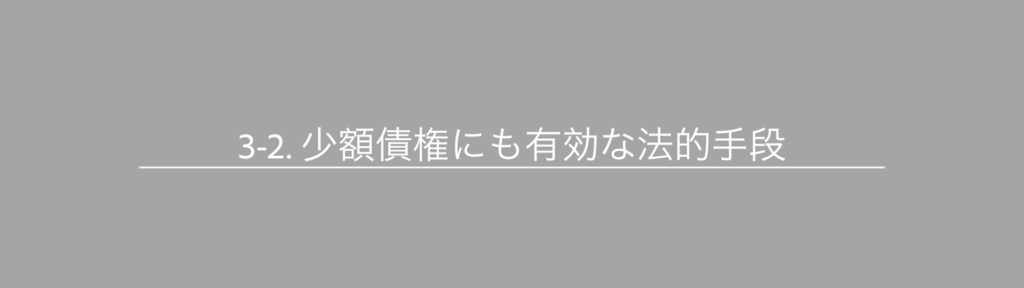
高額な費用をかけずに利用できる法的手段もあります。
- 少額訴訟(60万円以下の金銭債権):
- 特徴: 簡易裁判所で1回の審理で判決を目指す、迅速かつ安価な手続き。
- 利用条件: 60万円以下の金銭債権。
- メリット: 原則1日で審理が終了し、即日判決が得られる。費用も比較的安い。
- デメリット: 債務者が異議を唱えると通常訴訟に移行する。60万円を超える債権には使えない。
- 自社でやる場合: 簡易裁判所の窓口で相談しながら、訴状を作成・提出できます。ただし、法的な主張や証拠提出には準備が必要です。
- 支払督促:
- 特徴: 裁判所書記官が債務者に対し支払いを督促する手続き。債務者からの異議申立てがなければ、裁判を経ずに債務名義が得られる。
- 利用条件: 金銭の支払いを求める債権。債務者の住所が日本国内にあること。
- メリット: 訴訟よりも手続きが簡単で費用も安い。異議申立てがなければ迅速に債務名義を取得可能。
- デメリット: 債務者から異議申立てがあった場合、通常の訴訟に移行する。
- 自社でやる場合: 簡易裁判所に申立書を提出します。複雑な法律知識は不要ですが、正確な書類作成が求められます。
- 民事調停:
- 特徴: 裁判所が関与し、調停委員が間に入って債務者と話し合い、和解を目指す手続き。
- 利用条件: 双方の話し合いによる解決を望む場合。
- メリット: 費用が安い。話し合いのため、当事者間の関係悪化を避けやすい。調停成立後の調書は債務名義となる。
- デメリット: 相手方が調停に応じない場合や、合意に至らない場合は不成立となる。強制力はない。
- 自社でやる場合: 簡易裁判所に申立書を提出し、調停期日に出席します。相手との交渉力や落としどころを探る柔軟性が必要です。
表:自社でできる法的手段の比較
| 手段 | 費用目安(印紙代) | 期間目安 | 自分でできるか? | 必要知識レベル | 強制力 |
| 少額訴訟 | 数千円〜数万円 | 1ヶ月〜2ヶ月 | 可能(サポートあり) | 中 | あり |
| 支払督促 | 数千円 | 1ヶ月〜2ヶ月 | 可能 | 低〜中 | あり |
| 民事調停 | 数千円 | 1ヶ月〜数ヶ月 | 可能 | 低 | なし(合意による) |
3-3. 専門家への相談・依頼の検討タイミング
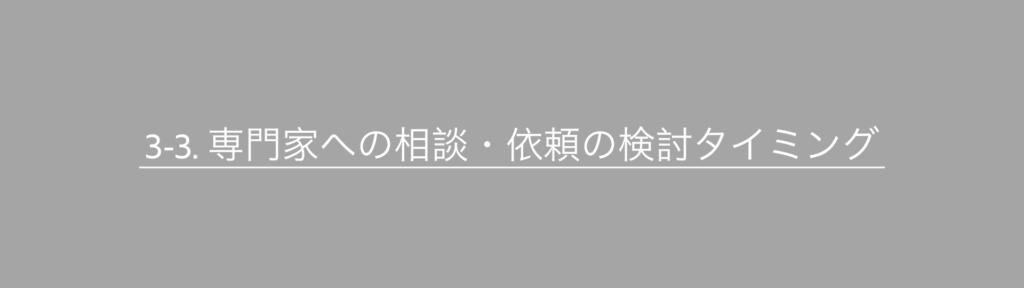
自社での督促や交渉、簡易な法的手段での対応に限界を感じたら、躊躇せず弁護士や司法書士に相談しましょう。
費用倒れのリスクも考慮し、最善の選択肢を提案してくれるでしょう。

第4章:未払い金を「作らない」ための予防策と最終的なリスクヘッジ
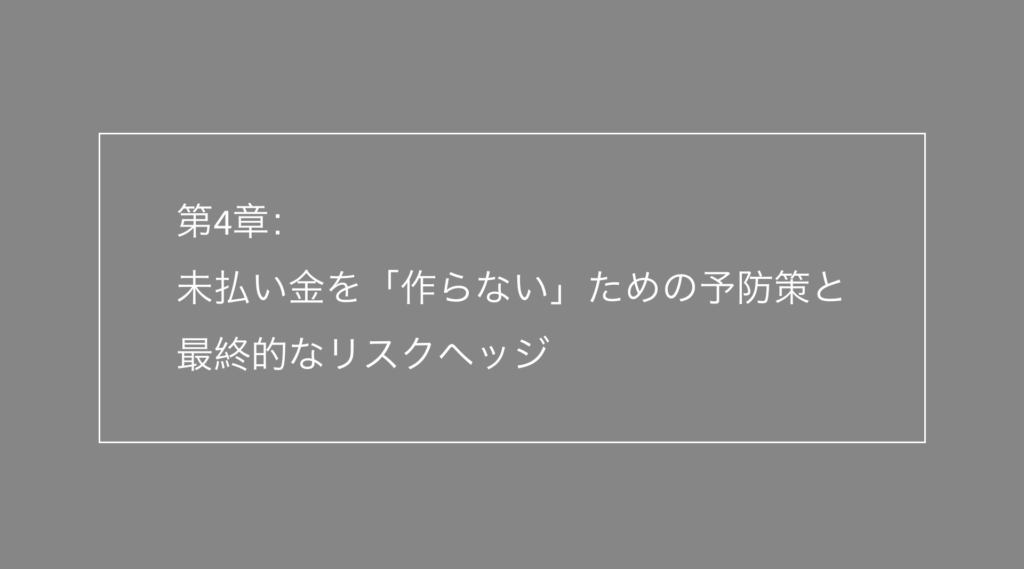
未払い金は、一度発生すると回収に多大な時間、労力、費用がかかります。
最も賢明な経営戦略は、そもそも未払い金が発生しないようにする「予防」、そして万が一発生してしまっても損失を補填できる「リスクヘッジ」です。
4-1. 未払い金を発生させないための予防策
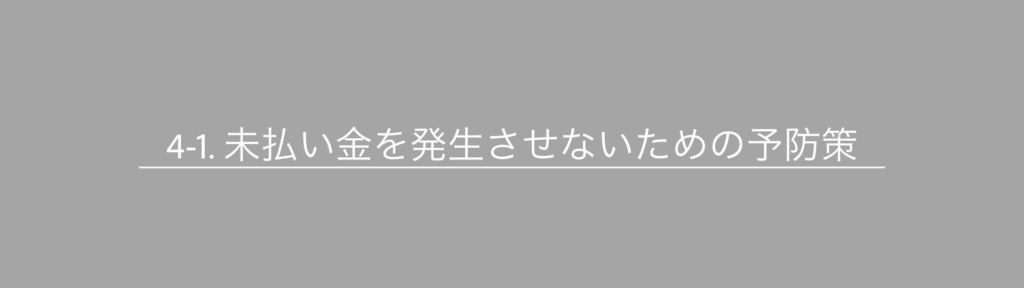
- 与信管理体制の強化と徹底:
- 新規取引先への徹底した信用調査: 取引を開始する前に、必ず信用調査会社(帝国データバンク、東京商工リサーチなど)のレポートを取得し、取引先の財務状況、支払い能力、過去の不祥事の有無などを詳細に確認しましょう。インターネットでの情報収集、登記情報の確認なども有効です。
- 与信限度額の設定と運用: 各取引先に対して、安全に売掛金を発生させられる上限額(与信限度額)を設定し、それを厳守します。定期的に見直しを行い、取引先の信用状況の変化に応じて調整しましょう。
- 取引先の継続的なモニタリング: 一度与信審査を通過した取引先であっても、経営状況は変化します。定期的に財務状況や業界情報をチェックし、支払い遅延の兆候や風評など、小さな異変も見逃さないようにしましょう。
- 与信管理規程の整備: 与信審査のプロセス、与信限度額の設定・運用方法、信用状況悪化時の対応などを文書化し、社内で共有・徹底します。これにより、担当者による判断のばらつきを防ぎ、組織的なリスク管理が可能になります。
- 契約条件の明確化と書面化:
- 口約束は厳禁: 全ての取引において、書面での契約を締結することを徹底します。契約書には、商品・サービスの内容、金額、納期、支払い期日、支払い方法、納品後の検収条件、クレーム対応、契約違反時の取り決めなどを明確に記載しましょう。
- 不利な条件は避ける: 支払いサイトが極端に長い取引や、検収条件が曖昧な取引は、未払いのリスクを高めます。可能な限り、自社にとって有利な条件で交渉し、書面に明記しましょう。
- 遅延損害金の設定: 支払期日を過ぎた場合に発生する遅延損害金の利率を明確に記載しておくことで、債務者に対し早期支払いを促す効果があります。
- 請求・入金管理の厳格化とシステム化:
- 請求書の正確な発行と送付: 請求書の内容(金額、請求日、期日、銀行口座情報など)に誤りがないか、複数人でチェックする体制を構築します。請求書の送付漏れや宛先の誤りがないよう、送付先リストを常に最新の状態に保ちましょう。
- 入金確認の徹底と早期発見: 支払期日前に「入金予定日」を確認し、期日になったら直ちに入金確認を行います。入金が確認できない場合は、システムで自動的にアラートが上がるようにするなど、早期に未払いを検知できる仕組みを構築しましょう。
- 債権管理システムの導入: 未払い金の発生から回収までのプロセスを効率的に管理できるシステム(例:会計ソフトの債権管理機能、専用の債権管理システムなど)を導入しましょう。これにより、債権ごとの状況、履歴、担当者、対応状況などを一元的に管理し、属人化を防ぎます。
- 定期的な残高確認: 定期的に取引先と売掛金残高の確認を行い、相違がないかを確認しましょう。これにより、債務者側の経理ミスなども早期に発見できます。
4-2. 最終的なリスクヘッジ:専門家との連携体制
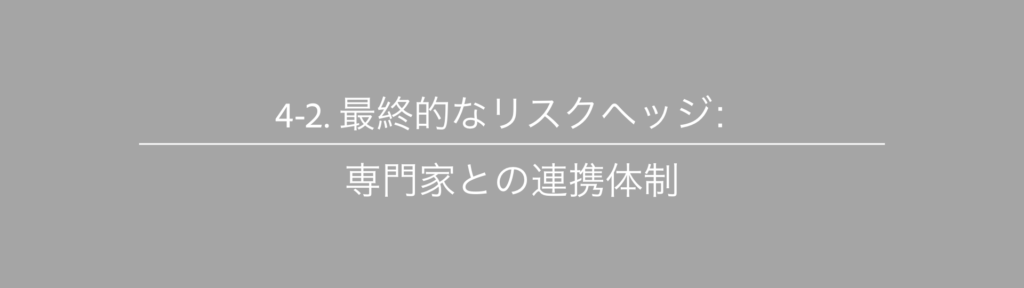
どんなに予防策を講じても、現代の不確実性の高いビジネス環境においては、取引先の突然の倒産や予期せぬ経営悪化など、自社では防ぎようのない未払いリスクは常に存在します。
- 顧問弁護士の活用:
- 日頃から顧問弁護士と契約しておくことで、未払い金が発生した際に、初期段階から専門的なアドバイスを受けられます。
- 契約書のチェックや与信管理体制の構築といった予防的な側面でもサポートを受けられ、未払い金の発生自体を減らすことにも繋がります。
- 債権回収専門の弁護士への相談:
- 顧問弁護士がいない場合でも、債権回収を専門とする弁護士事務所を探し、いざという時に迅速に相談できるリストアップをしておきましょう。
- 特に、自社での回収が難航している、相手が悪質、金額が大きい、といった場合には、迷わず弁護士に相談すべきです。弁護士は、あなたの会社の代わりに交渉し、必要であれば法的手続きを迅速に進めてくれます。
4-3. 予防とリスクヘッジで安定経営を
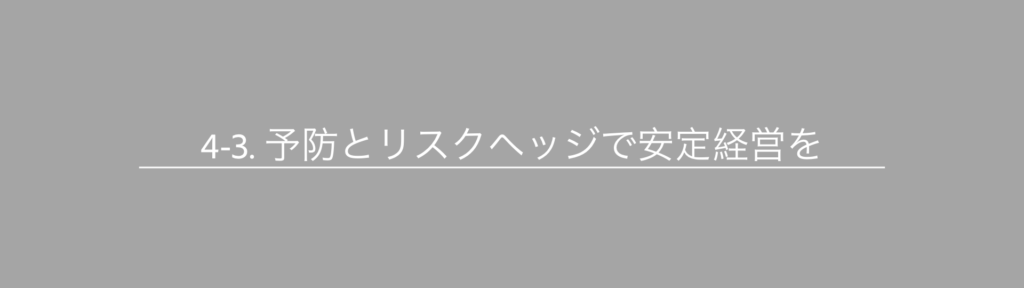
未払い金の回収は、一旦発生してしまえば、多大な時間と労力がかかります。
最も理想的なのは、そもそも未払い金が発生しない仕組みを作り上げることです。
強固な与信管理と厳格な債権管理は、その基盤となります。
しかし、どんなに完璧な予防策を講じても、リスクをゼロにすることは不可能です。

結論:自社でできる初期対応を徹底し、未払い金は今すぐ債権回収しましょう!
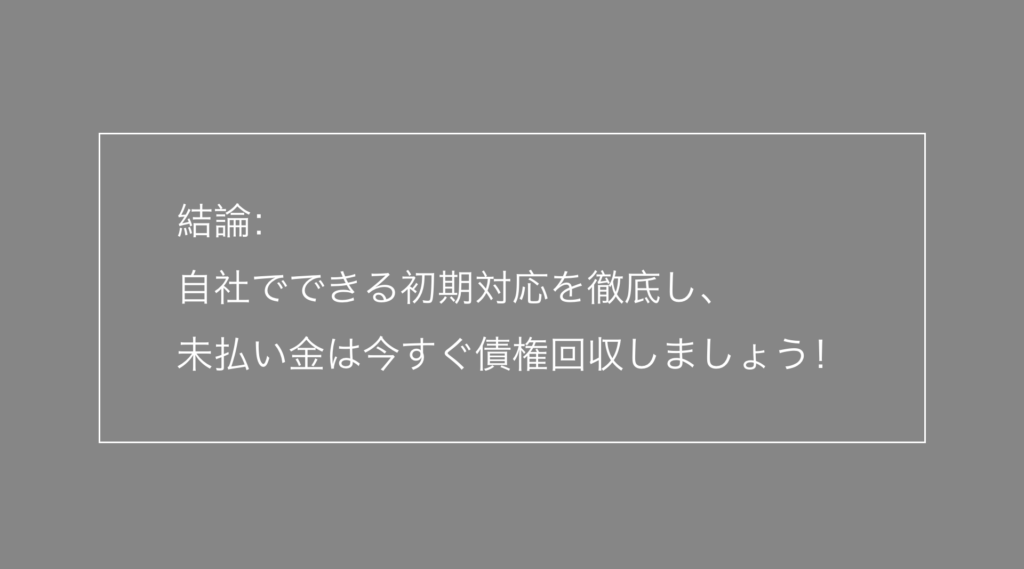
未払い金は、企業のキャッシュフローを蝕む静かなる脅威です。
スピードを意識し、証拠を確実に保全し、冷静かつ毅然とした態度で臨むことが成功の鍵となります。
また、自社での対応に限界を感じたら、早めに弁護士や司法書士といった専門家への相談を検討することも重要です。
彼らは、あなたの貴重な売掛金を守るための強力なパートナーとなるでしょう。
強固な与信管理体制と厳格な債権管理を徹底し、あなたの会社を未払いリスクから守りましょう。
どんなに予防しても、経済状況の変動や取引先の不測の事態によって、未払い金が発生するリスクを完全に排除することはできません。しかし、その「万が一」の際にも、決して諦めてはいけません。
【補足:成功報酬で債権回収するならXP法律事務所とは】
XP法律事務所は、債権回収を成功報酬で行います。
ご興味ある方は下記から相談

債権回収に関してご相談
