債権回収
未払金を回収する10個の方法とは?回収方法について解説
未払い金を回収する10個の効果的な方法を徹底解説。自力督促から内容証明、法的手段、専門家依頼、そして時効対策まで網羅。あなたの会社の資金を確実に守るための実践的な回収術をご紹介します。

序章:未払い金は放置厳禁!あなたの会社の資金を守るための実践ガイド
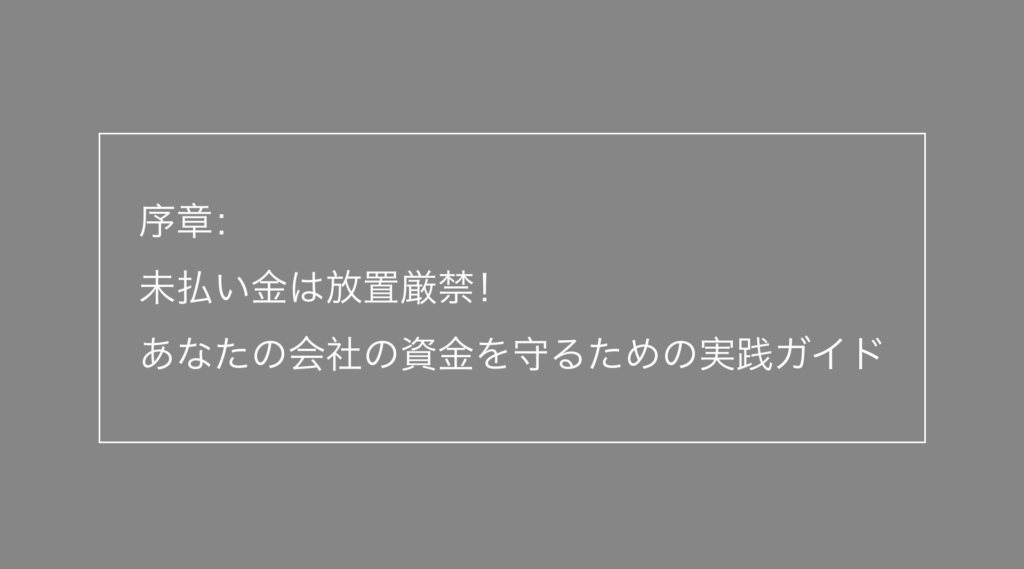
商品やサービスを提供したにもかかわらず、顧客からの支払いが滞ってしまう「未払い金」は、企業のキャッシュフローを悪化させ、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
多くの企業が、一度は直面するこの問題に対し、「どうすればいいのか」「どこまで対応すべきか」と頭を抱えていることでしょう。
「あの顧客だから、もう少し待っても大丈夫だろう…」 「督促の連絡は、関係を悪化させるのではないか…」 「法的な手続きは費用がかかるし、複雑そう…」
このような思いから、つい未払い金を放置してしまいがちですが、それは大きな間違いです。
時間が経てば経つほど、未払い金は回収が困難になり、最終的には「貸倒損失」として計上せざるを得なくなる可能性が高まります。
もう未払い金に悩む必要はありません。
あなたの会社の正当な売上と未来を守るために、今こそ行動を起こしましょう。

第1章:未払い金回収の基本と心構え:なぜ「スピード」が重要なのか
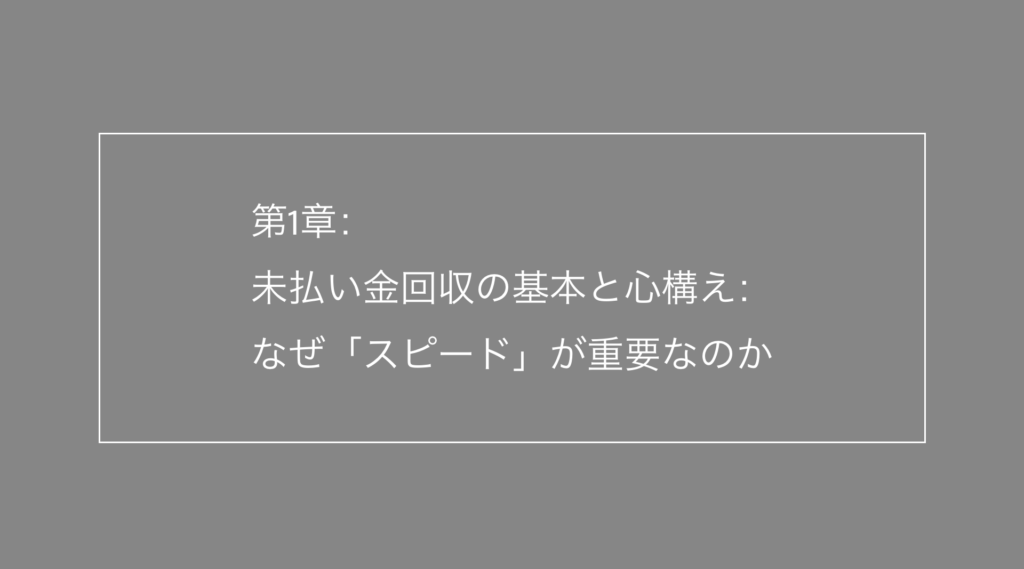
未払い金回収の具体的な方法に入る前に、まずは未払い金に対する基本的な理解と、回収に臨む上での心構えを確立することが重要です。
1-1. 未払い金とは?その種類と放置のリスク
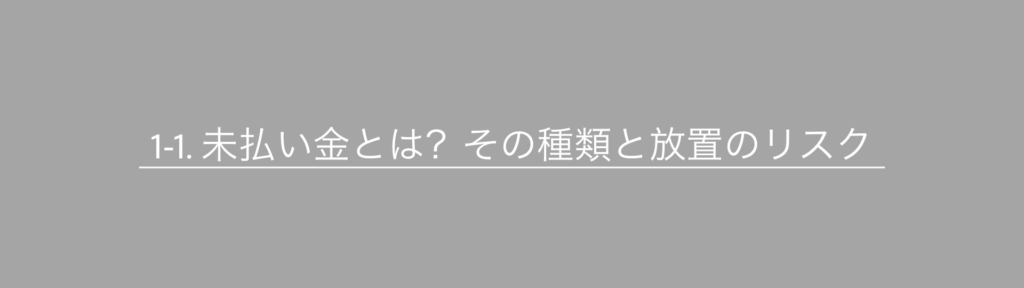
未払い金とは、企業が商品やサービスを提供したにもかかわらず、その代金が支払期日までに支払われていない金額全般を指します。
企業会計上は、主に以下の勘定科目で管理されます。
- 売掛金: 通常の営業活動(商品の販売やサービスの提供)によって発生する未収の代金。
- 未収入金: 営業活動以外で発生する未収の金銭(例:固定資産の売却代金、貸付金など)。
これらの未払い金は、帳簿上は「資産」として計上されますが、実際に現金として手元になければ、以下のリスクを招きます。
- キャッシュフローの悪化:
- 企業は、売上だけでなく、実際に回収した現金で日々の仕入れ、人件費、家賃などの経費を賄っています。未払い金が増えれば、いくら帳簿上の売上が高くても手元の資金が不足し、資金繰りが悪化します。これが続くと、黒字倒産という事態に陥る可能性すらあります。
- 貸倒損失の発生:
- 未払い金が最終的に回収不能となった場合、それは貸倒損失として企業の利益を圧迫します。税務上の損金処理は可能ですが、一度失われた現金は戻りません。
- 回収率の低下:
- 債権回収は「時間との勝負」です。 債権は時間が経てば経つほど、回収が困難になる傾向があります。
- 債務者(支払うべき相手)の経営状況が悪化する、倒産する可能性がある。
- 債務者と連絡が取れなくなる(夜逃げ、行方不明)。
- 時効が迫る(債権には時効があり、一定期間で回収できなくなる)。
- 債務者が他の債権者への支払いを優先する。
- 債権回収は「時間との勝負」です。 債権は時間が経てば経つほど、回収が困難になる傾向があります。
- 企業信用度の低下:
- 未払い金を放置する企業は、管理体制が甘いと見なされ、金融機関からの融資審査や、新たな取引先との契約において不利になる可能性があります。
1-2. 回収成功率を高める「スピード」の重要性
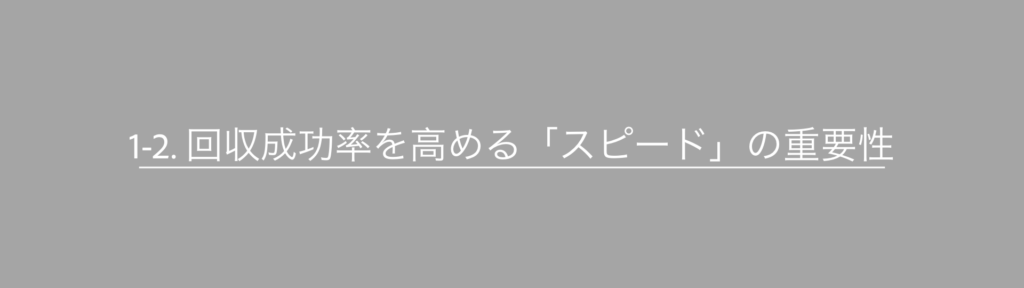
未払い金回収において、最も重要な要素の一つが「スピード」です。
グラフ:未払い期間と回収成功率の関係(一般的な目安)
| 未払い期間 | 回収成功率の目安 |
| 1週間以内 | 90%以上 |
| 1ヶ月以内 | 70%〜80% |
| 3ヶ月以内 | 50%〜60% |
| 6ヶ月以内 | 30%〜40% |
| 1年以上 | 10%以下 |
このグラフが示すように、未払い期間が長くなればなるほど、回収成功率は急激に低下します。
1-3. 債権の時効と「証拠」の重要性
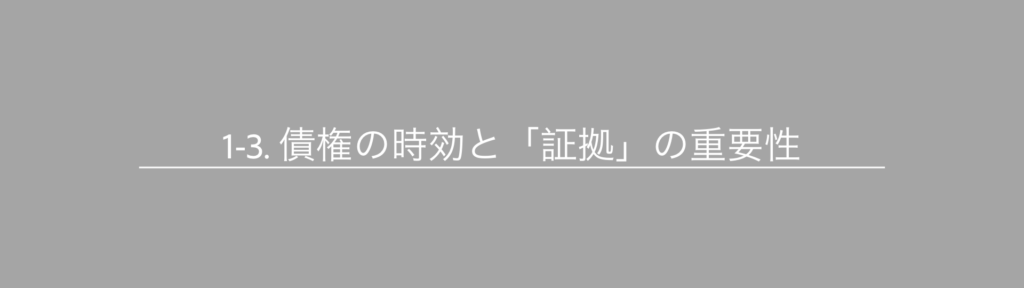
債権には時効があり、一定期間が経過すると、債務者が時効を主張することで回収できなくなります。
原則として支払期日から5年(改正民法による)。
時効の進行を止める(時効の更新)ためには、以下の行動が有効です。
- 債務の承認: 債務者が支払い義務を認めること(例:一部弁済、支払い猶予の依頼など)。
- 請求: 裁判上の請求(訴訟の提起、支払督促の申立てなど)や、内容証明郵便による催告(6ヶ月間の時効完成猶予効果)。
これら全ての書類や記録を、時系列で整理し、完璧に保管することが、未払い金回収の成功を左右する最も重要な要素となります。

第2章:未払い金を回収する10個の方法【自社でできる初期対応編】
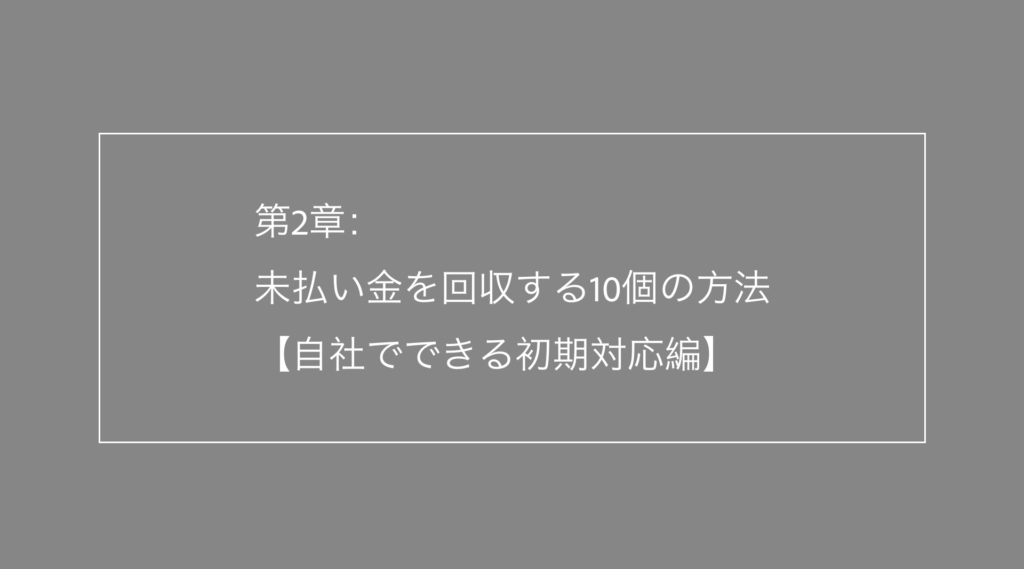
未払い金が発生した際、まずは自社でできる範囲での初期対応を迅速に行うことが重要です。
ここからは、具体的な10個の回収方法を段階的に解説していきます。
方法1:支払期日直後の「確認連絡」(最も穏やかなアプローチ)
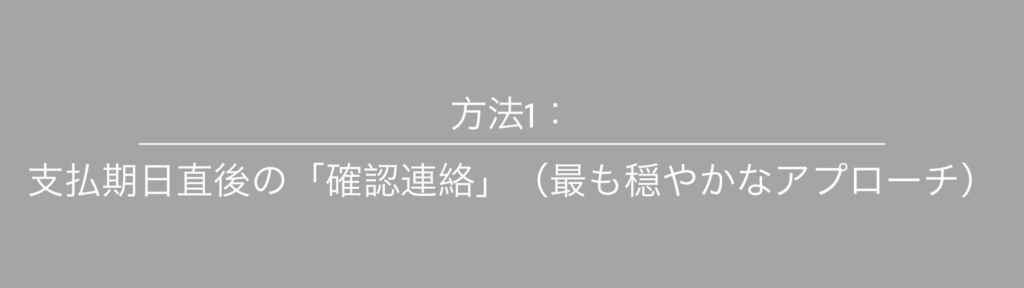
- 目的: 支払い忘れや事務処理ミスを確認し、支払いを促す。顧客との良好な関係性を維持しつつ、早期解決を目指す。
- タイミング: 支払期日の翌日〜数日以内(最も効果的)。
- 方法:
- 電話(最優先): 債務者(顧客)の担当者または経理担当者へ直接連絡。
- 伝え方例: 「〇月〇日付の請求書の件ですが、お振込の確認が取れていないようです。何かお手続き上の問題がありましたでしょうか?」など、丁寧かつ事務的な口調で確認。決して責める口調にならず、あくまで**「確認」のスタンス**を徹底します。
- 聞くべきこと: 未払いの理由、具体的な支払い予定日(曖昧な返答は許さず、「月末」ではなく「〇月〇日」と日付を明確に)。
- メール: 電話で連絡が取れない場合や、電話での会話内容の確認として送付。件名は「〇月分ご請求に関するご確認(〇〇株式会社)」など、緊急性を伝えるが、威圧的にならないように注意する。請求書を再添付し、振込先情報を改めて明記する。
- 電話(最優先): 債務者(顧客)の担当者または経理担当者へ直接連絡。
方法2:再請求書の送付
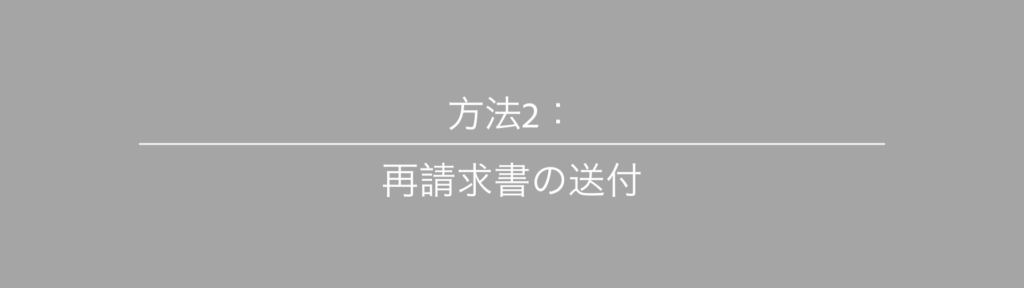
- 目的: 支払い期日を過ぎた請求書を改めて送付し、支払いを促す。
- タイミング: 支払期日の1週間後〜10日後(方法1と並行して行うことも可能)。
- 方法:
- 「再請求書」であることを明記し、元の請求書と区別できるようにする。
- 支払期日を新たに設定し、遅延していることを明確に伝える。
- 「本状と行き違いにご入金の場合はご容赦ください」といった文言を添え、丁寧な印象を保つ。
方法3:督促状(催告書)の送付(普通郵便/特定記録郵便)
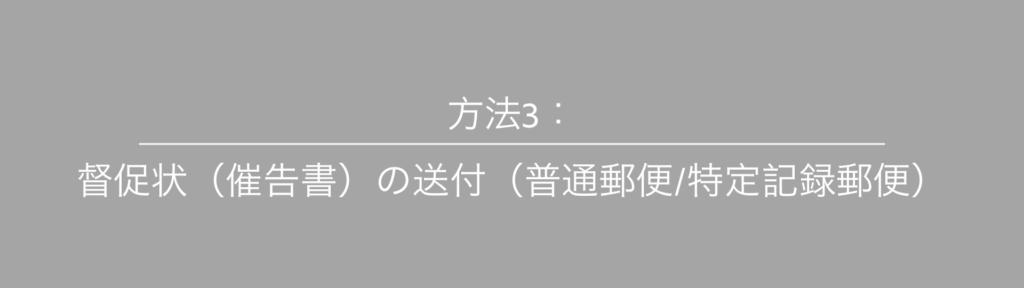
- 目的: 書面で正式に支払いを催促し、心理的プレッシャーを強める。
- タイミング: 支払期日の1週間後〜1ヶ月後(方法1・2で反応がない場合)。
- 方法:
- 督促状の作成:
- 未払い債権の詳細(請求書番号、金額、支払期日、取引内容)を明確に記載。
- これまでの連絡経過(例:〇月〇日の電話にて支払い確認が取れていませんが、その後ご入金がございません)を簡潔に記載。
- **「〇月〇日までに〇円の支払いをお願いいたします」**と具体的な支払い期日を設け、この期日までに支払いがない場合は次のステップ(法的手段など)に進む可能性を示唆する。
- 遅延損害金が発生する旨も明記し、計算方法も記載する(契約書に定めがある場合)。
- 送付方法:
- 普通郵便: 簡易な督促。
- 特定記録郵便: 発送と受領の事実を郵便局が記録してくれるため、相手が「受け取っていない」と主張するのを防げる。
- 督促状の作成:
方法4:内容証明郵便の送付(最終警告)
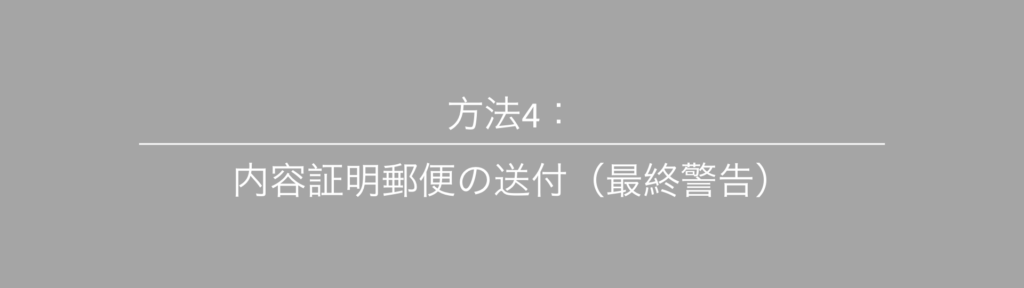
- 目的: 法的措置を視野に入れていることを明確に伝え、債務者への心理的プレッシャーを最大限に高める。時効の更新(中断)効果もあるため、時効が迫っている場合にも有効。
- タイミング: 支払期日の1ヶ月〜3ヶ月後(方法1〜3で反応がない、または不誠実な対応が続く場合)。
- 方法:
- 内容:
- 債権の発生原因(売買契約など)、未払い金額、支払期日を明確に記載。
- これまでの督促経過(〇月〇日に電話、〇月〇日に督促状送付など)を簡潔に記載。
- **「本状到着後、〇日以内(通常1週間~10日程度)に支払いがない場合、やむを得ず法的手段に移行する」**旨を明確に通知する。
- 遅延損害金が発生する場合は、その具体的な計算方法と金額も明記する。
- 送付方法: 郵便局で「内容証明郵便」として送付。同時に**「配達証明」**も付けることで、相手がその書面をいつ受け取ったかという事実を公的に証明できます。
- 内容:
方法5:債務者との直接交渉・支払い計画の提案
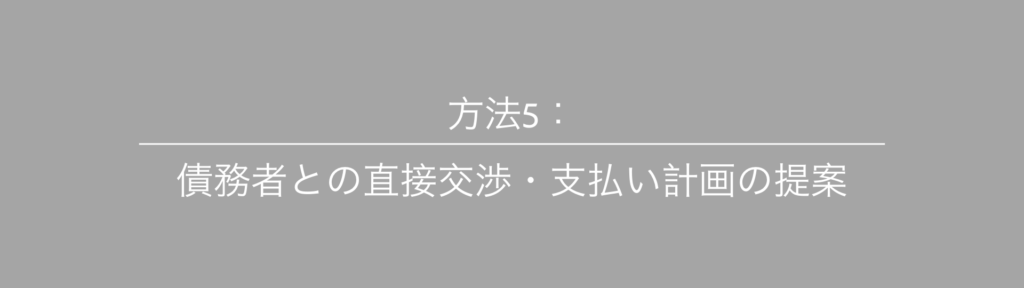
- 目的: 債務者の支払い意思や具体的な状況を確認し、回収に向けた合意を形成する。
- タイミング: 債務者から連絡があった場合、または内容証明郵便送付後。
- 方法:
- 面談または電話会議: 債務者と直接対話することで、背景にある問題を把握し、解決策を探ります。
- 支払い能力の確認: 債務者がなぜ支払えないのか、その理由を深く掘り下げて聞く。資金繰りの状況などを可能な範囲で確認する。
- 支払い計画の提案:
- 分割払い: 債務者が一括払いが難しい場合、無理のない分割払いを提案。ただし、必ず「債務承認弁済契約書」または「和解契約書」を作成し、公正証書としておくことで、不履行時の強制執行が可能となります。
- 支払い期日の延長: 短期間の延長であれば、猶予を与えることも検討。
- 一部弁済・債務減額: 回収が非常に難しいと判断した場合、一部を諦めてでも確実に回収できる金額で合意する(ただし慎重な判断が必要)。
- 公正証書の作成: 合意内容を公正証書にしておくことで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。

第3章:未払い金を回収する10個の方法【法的手段・専門家への依頼編】
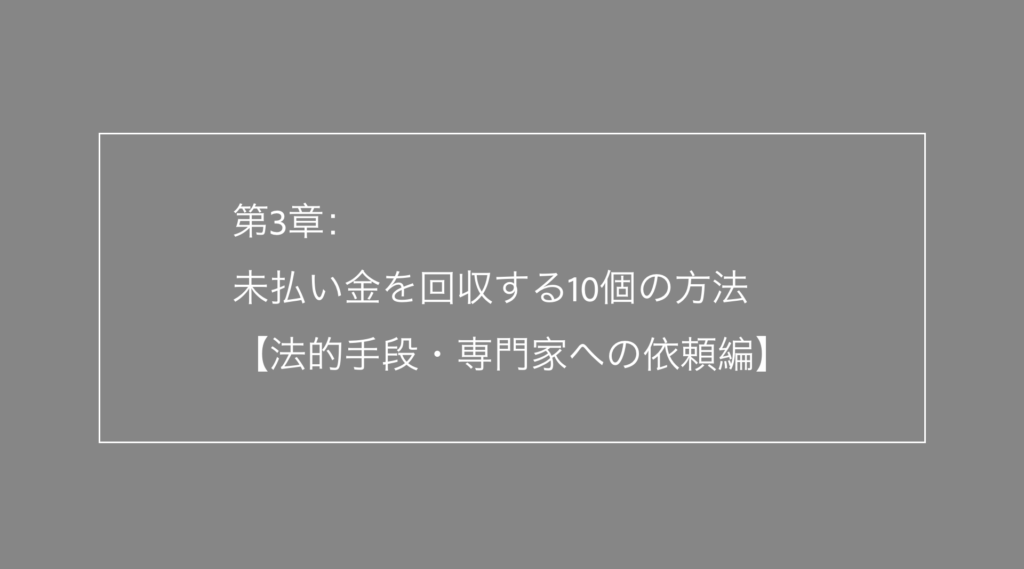
自力での督促や交渉で回収が困難な場合、あるいは債務者が悪質な場合、法的な強制力を持つ手段や専門家の力を借りることを検討します。
方法6:少額訴訟(60万円以下の未払い金)
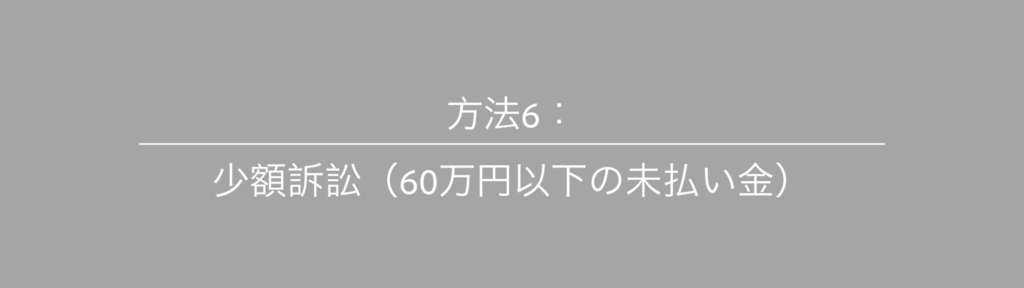
- 目的: 簡易裁判所の迅速な手続きで判決を得て、強制執行の根拠とする。
- タイミング: 自力回収で成果がない場合、未払い金額が60万円以下の場合。
- 特徴:
- 簡易裁判所で行われる、原則として1回の審理で判決を目指す、迅速かつ簡便な手続き。
- 費用が比較的安い。
- 個人や企業自身でも手続きしやすい。
- 弁護士・司法書士への依頼: 司法書士は140万円以下の案件であれば代理可能。弁護士は金額問わず代理可能。
方法7:支払督促
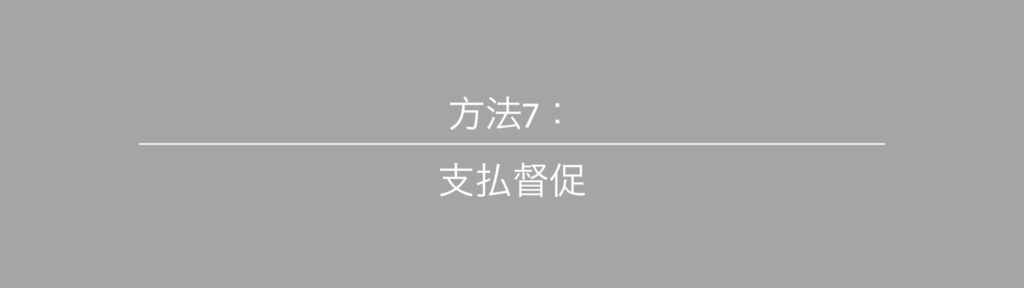
- 目的: 裁判所書記官に督促状を発行してもらい、債務者が異議を唱えなければ、裁判を経ずに強制執行を可能にする債務名義を得る。
- タイミング: 債務者から異議が出る可能性が低いと判断される場合。
- 特徴:
- 裁判所に出廷する必要がないため、手続きが簡単で費用も安い(訴訟の半額程度)。
- 債務者から異議申立てがなければ、比較的迅速に「仮執行宣言付き支払督促」という債務名義を取得できる。
- 弁護士・司法書士への依頼: 司法書士は140万円以下の案件であれば代理可能。弁護士は金額問わず代理可能。
方法8:民事調停
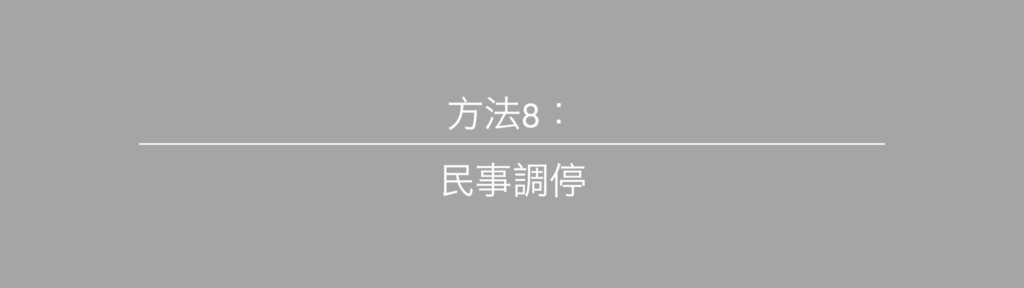
- 目的: 裁判所の調停委員を介して、債務者と話し合い、和解を目指す。
- タイミング: 債務者と対話の余地があり、柔軟な解決を目指したい場合。
- 特徴:
- 費用が安い。
- 話し合いのため、当事者間の合意形成を促し、柔軟な解決(分割払いなど)が可能。
- 調停が成立すれば、その内容を記載した「調停調書」は債務名義となる。
- 今後の取引関係を完全に断ち切らずに解決したい場合に有効。
- 弁護士・司法書士への依頼: 司法書士は140万円以下の案件であれば代理可能。弁護士は金額問わず代理可能。
方法9:通常訴訟
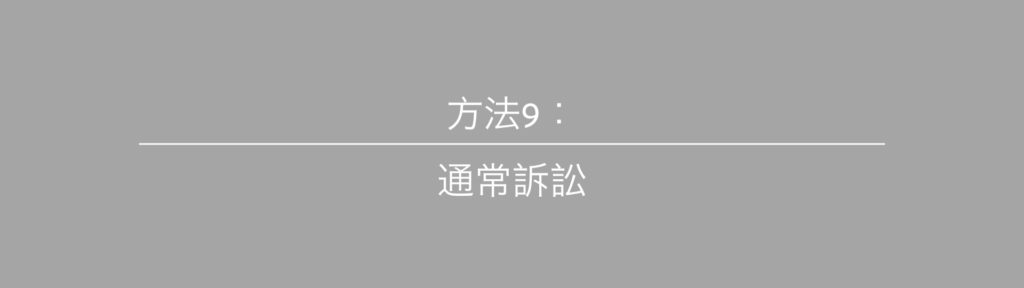
- 目的: 裁判所の判決を得て、未払い金の支払いを法的に確定させ、強制執行の根拠とする。
- タイミング: 未払い金額が高額な場合、債務者が徹底的に支払いを拒否し争う姿勢を見せている場合。
- 特徴:
- 未収金額に制限がない。
- 判決が出れば、強制執行が可能になる。
- 複雑な契約問題や損害賠償請求も同時に主張できる。
- 弁護士への依頼: 専門知識が必要なため、弁護士への依頼が必須。
方法10:強制執行(最終手段)
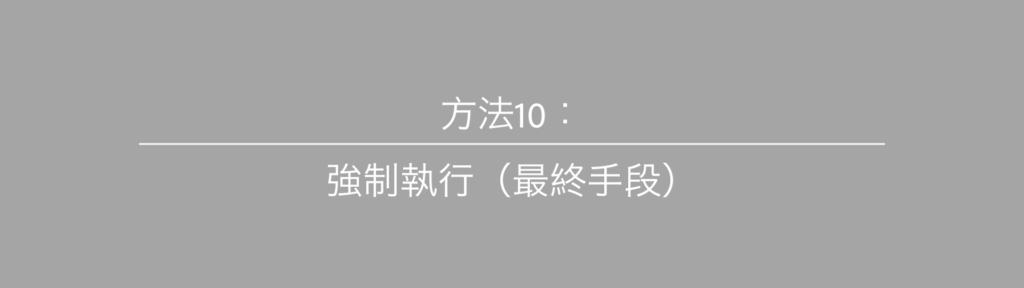
- 目的: 裁判所の判決や調停調書、公正証書などの債務名義に基づいて、債務者の財産(預金、不動産、給与、動産、他の債権など)を差し押さえ、強制的に未払い金を回収する。
- タイミング: 他の法的手段で債務名義を取得したが、債務者が任意に支払わない場合。
- 特徴: 債務者の意思に関わらず、強制的に未払い金を回収できる。
表:未払い金回収の10個の方法の比較
| 方法 | 分類 | 費用目安 | 期間目安 | 強制力 | 成功率(自社努力) | 難易度(自社実施) | こんな時に有効 |
| 1. 確認連絡 | 自社対応 | 低 | 数日 | 低 | 高 | 低 | 支払い忘れ、事務ミス。関係維持優先。 |
| 2. 再請求書 | 自社対応 | 低 | 1週間 | 低 | 中 | 低 | 請求書紛失、確認漏れ。 |
| 3. 督促状 | 自社対応 | 低 | 1ヶ月 | 低 | 中 | 低 | 支払い意思はあるが遅延。 |
| 4. 内容証明 | 自社対応 | 中 | 1〜3ヶ月 | 中 | 中 | 中 | 最終警告。法的手段示唆。時効対策。 |
| 5. 直接交渉 | 自社対応 | 中 | 数ヶ月 | 低 | 中 | 中 | 支払い意思があるが困難。分割検討。 |
| 6. 少額訴訟 | 法的手段 | 低〜中 | 1〜2ヶ月 | 高 | 高(判決後) | 中 | 60万円以下の少額債権。 |
| 7. 支払督促 | 法的手段 | 低〜中 | 1〜2ヶ月 | 高 | 高(異議なし) | 中 | 異議なく支払い見込み。 |
| 8. 民事調停 | 法的手段 | 低 | 1〜数ヶ月 | 低 | 中(和解成立) | 中 | 関係維持しつつ柔軟な解決。 |
| 9. 通常訴訟 | 法的手段 | 高 | 数ヶ月〜年単位 | 高 | 高(判決後) | 高 | 高額債権。争う姿勢が強い。 |
| 10. 強制執行 | 法的手段 | 高 | 数ヶ月〜 | 極高 | 高(財産あれば) | 高 | 債務名義取得済みで未払い。 |

第4章:未払い金を未然に防ぐための予防策
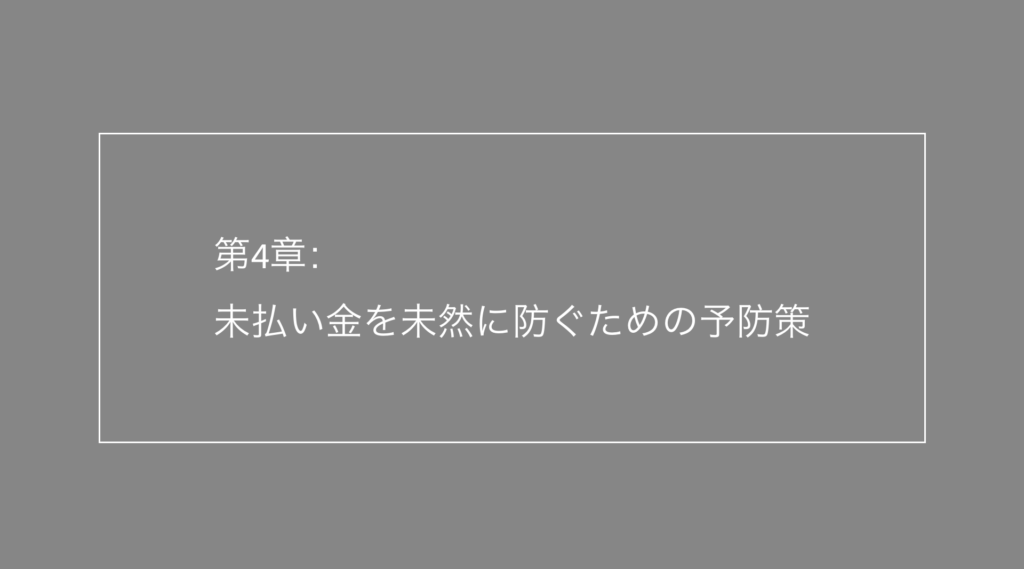
4-1. 契約前の与信管理の徹底
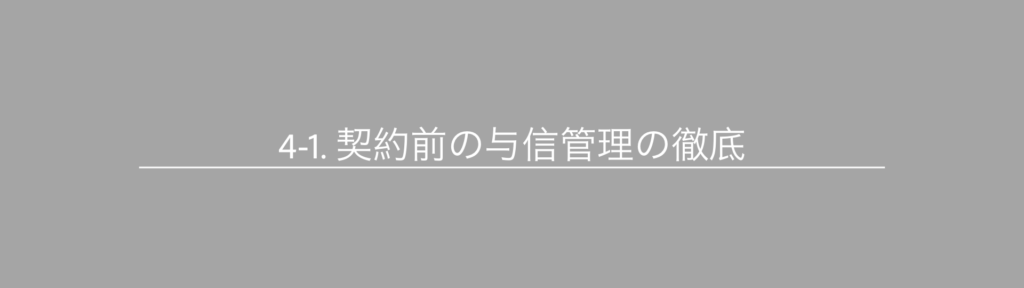
- 新規取引先の信用調査: 帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社を利用し、財務状況、代表者の情報、過去のトラブル履歴などを確認する。インターネットやSNSでの評判もチェック。
- 契約条件の明確化: 支払期日、支払い方法、遅延損害金、契約解除条件などを契約書に明確に記載する。曖昧な点は残さない。
- 担保・保証の検討: 大口の取引や信用に不安がある場合、連帯保証人を立ててもらう、保証金を預かる、動産・不動産に担保を設定するなどの対応も検討する。
4-2. 契約書・請求書の厳格な運用
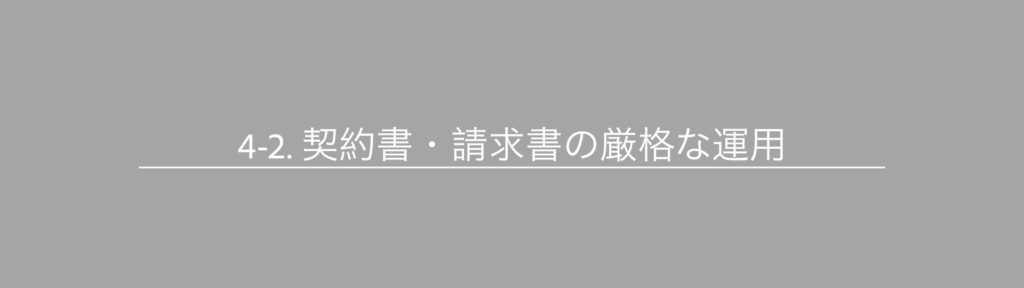
- 書面契約の徹底: 口約束での取引は極力避け、必ず書面で契約を締結する。
- 請求書の迅速な発行: 商品やサービスの納品・提供後、速やかに請求書を発行し、顧客に送付する。
- 請求書の記載漏れ・誤記の防止: 金額、支払期日、振込先など、記載内容に誤りがないか複数人で確認する。
- 請求書送付後の確認: 請求書を送付した旨をメールなどで伝え、相手が確実に受け取ったかを確認する。
4-3. 支払い状況の定期的なモニタリング
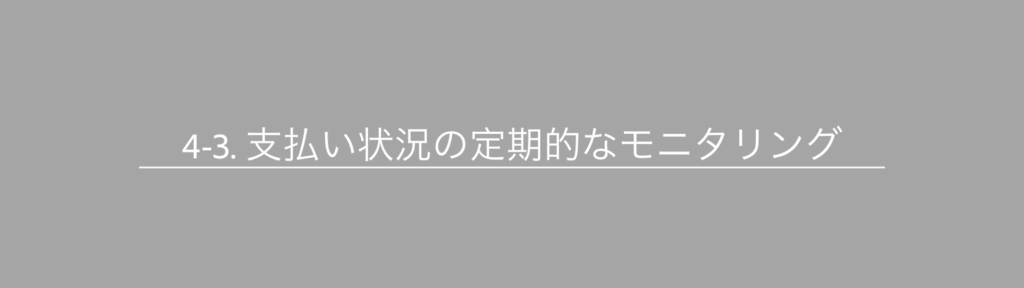
- 支払い期日管理の徹底: 会計システムや専用のソフトを活用し、請求書の支払期日を正確に管理する。
- 入金状況の定期的なチェック: 支払い期日が近づいたら、あるいは過ぎたら、入金状況を毎日チェックする。
- 兆候の察知: 支払い遅延が頻繁になる、連絡がつきにくくなる、担当者が変わる、取引先の悪い噂を耳にするなどの兆候があれば、すぐに警戒し、対応を検討する。
4-4. 売掛金保証(取引信用保険)の活用
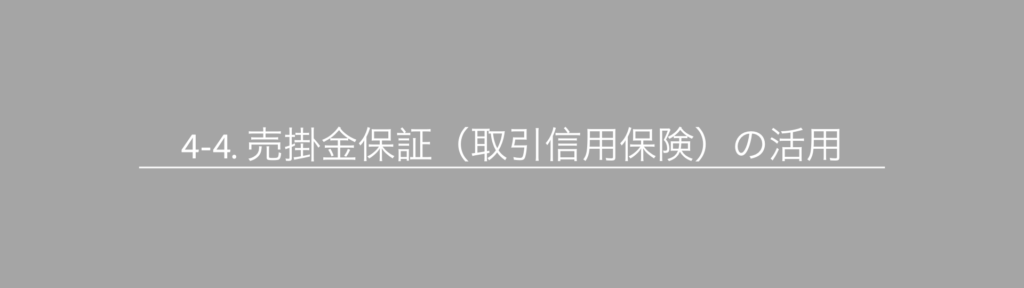
- 究極のリスクヘッジとも言えるのが、**売掛金保証(取引信用保険)です。これは、取引先の倒産や長期の支払い不能により売掛金が回収不能になった際に、保険会社がその損失を補填してくれるサービスです。
- メリット: 貸し倒れ損失から会社を守り、資金繰りを安定させる。与信管理を客観的に行える。本来ならリスクの高い新規取引先とも安心して取引できるようになる。
- デメリット: 保険料がかかる。全ての債権が対象となるわけではない。

結論:未払い金は放置せず、あなたの会社の資金を守りましょう!
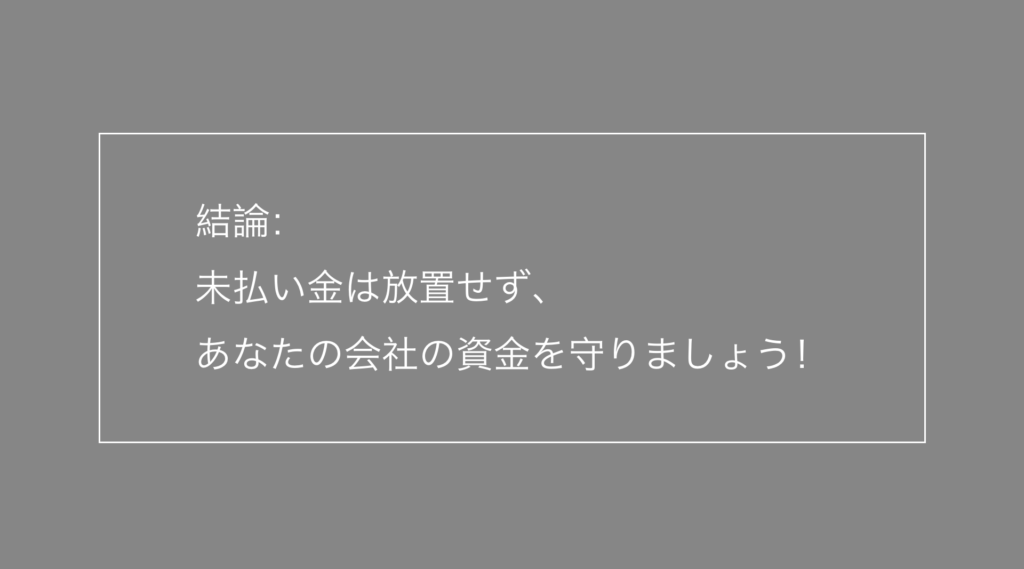
本記事で解説したように、未払い金を回収するためには、自社での迅速かつ段階的な督促から始まり、内容証明郵便の活用、そして必要に応じて法的手段や専門家の力を借りるという、明確なステップが存在します。
重要なのは、感情的にならず、法的なリスクを回避しつつ、冷静かつ毅然とした態度で臨むことです。
【補足:成功報酬で債権回収するならXP法律事務所とは】
XP法律事務所は、債権回収を成功報酬で行います。
ご興味ある方は下記から相談

債権回収に関してご相談
FAQ
①売掛保証・債権保証とは?
売掛保証とは、企業が商品やサービスを販売した際に発生する売掛金(未回収の代金)が、取引先の倒産や支払い遅延などで回収できなくなった場合に、保証会社や保険会社がその損失を補償してくれるサービスです。
これは、債権保証とも呼ばれ、企業の資金繰り安定や貸倒れリスクの軽減を目的としています。売掛保証を導入すれば、安心して新規取引や大口契約に挑戦でき、事業拡大を後押しする効果が期待できます。いわば、会社の売上を守る「安心の保険」のようなものです。
申し込みはこちら:https://toshika-lp.protocol.ooo/protocol-deal
②債権回収・未払い回収とは?
債権回収とは、企業や個人が、商品やサービスの提供、または貸付などによって発生した「債権」(お金を受け取る権利)について、約束の期日になっても相手方(債務者)から支払いがない場合に、そのお金を取り戻すための一連の活動を指します。
具体的には、支払いの催促(督促)、交渉、そして最終的には法的手段(内容証明郵便の送付、少額訴訟、通常訴訟、強制執行など)を通じて、未回収の資金を回収するプロセスです。会社の資金繰りを健全に保つ上で非常に重要な業務です。
申し込みはこちら:https://xp-law.com/saikennkaisyuu
