債権回収
債権回収の専門家が語る!絶対にやってはいけないNG行動
未払い金の回収でやってはいけないNG行動を、債権回収の専門家が徹底解説。法的なリスクやトラブルを避けるための注意点から、効果的な正しいアプローチまで、安全かつ確実に回収するためのノウハウを伝授します。

序章:回収の「焦り」が招く法的リスクとトラブル
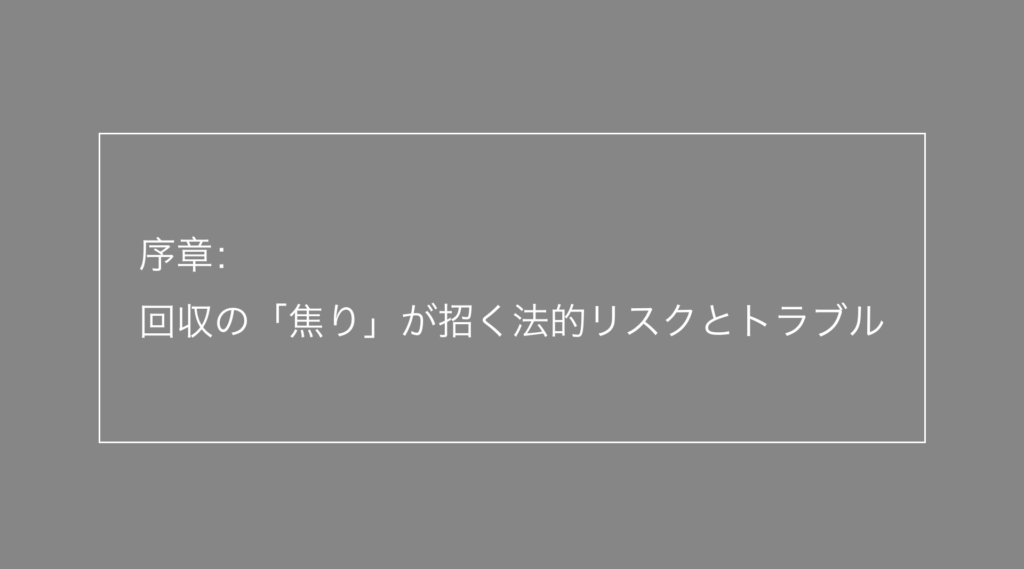
しかし、この「焦り」や「不適切な感情」が、後で取り返しのつかない事態を招く可能性があります。
- 「相手の家に押しかけてしまった…」
- 「電話で怒鳴ってしまい、脅迫だと訴えられた…」
- 「会社のホームページで悪口を書いてしまった…」
これらはすべて、債権回収において絶対にやってはいけないNG行動です。良かれと思って行った行動が、法律違反となり、逆に損害賠償請求を受けたり、企業の信用を失ったりするリスクにつながります。特に、債務者が悪質な場合、こちら側の不手際を虎視眈々と狙っていることも少なくありません。

第1章:違法行為に繋がるNG行動:あなたの正義が危険な行為に変わる時
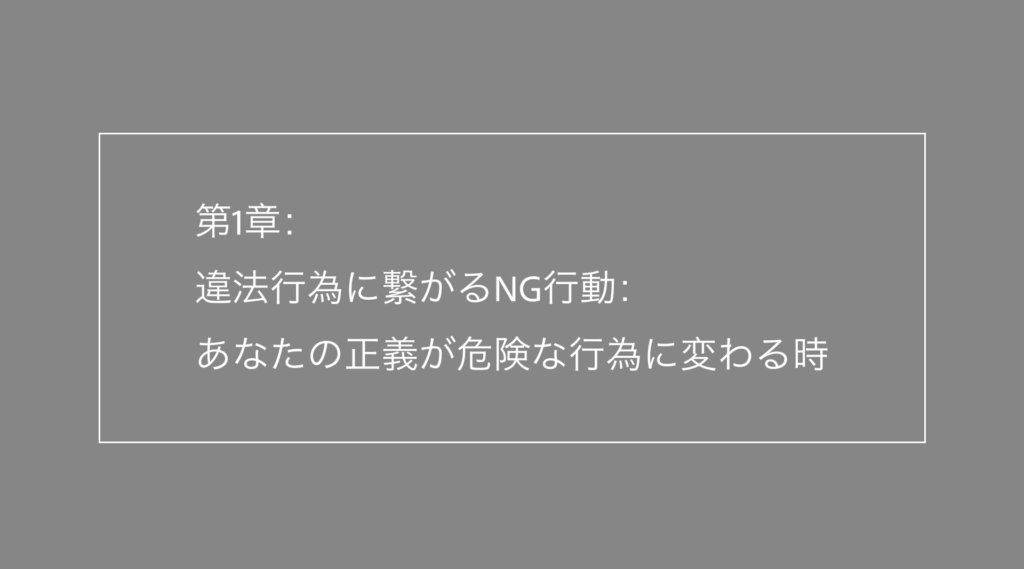
債権回収は、法的な枠組みの中で行わなければなりません。
法律に違反する行為は、損害賠償請求や刑事罰の対象となり、あなたの会社を窮地に追い込むことになります。
1-1. 債務者への直接的な「精神的・物理的攻撃」
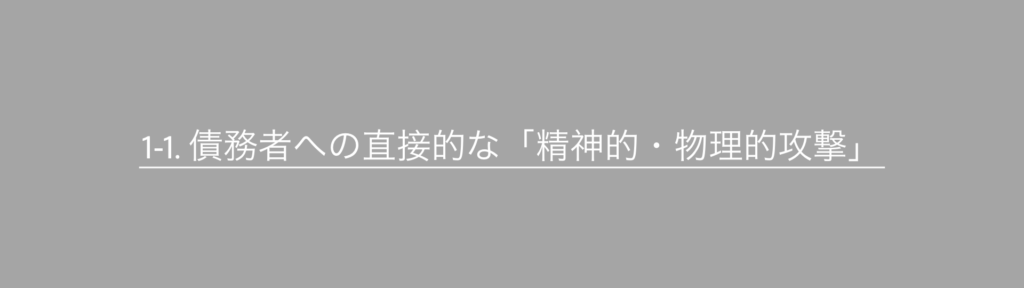
- 脅迫・暴力行為:
- NG行動: 「払わなければ家族にも連絡するぞ」「お前の会社を潰してやる」「二度と商売できないようにしてやる」といった言葉を浴びせたり、脅したりすること。また、殴る、蹴る、物を壊すといった暴力行為。
- 法的リスク:
- 恐喝罪: 財産上の不法な利益を得る目的で、脅迫や暴行を加えた場合に成立します。
- 強要罪: 義務のないことを行わせる目的で、脅迫や暴行を加えた場合に成立します。
- 暴行罪・器物損壊罪: 暴力や物の破壊に対して成立します。
- 民事上の損害賠償請求: 脅迫や暴力によって債務者に精神的・物理的な損害を与えた場合、不法行為として慰謝料を請求される可能性があります。
- 専門家の見解: 債務者から「怖い取り立てをされた」と証拠(録音など)を突きつけられた場合、一転してあなたが加害者となり、本件の債権回収はほぼ不可能になります。
- 不退去罪・住居侵入罪:
- NG行動: 債務者の自宅やオフィスを訪問し、相手が「帰ってください」と言っても居座り続けること。また、相手の許可なく敷地内に立ち入ること。
- 法的リスク:
- 不退去罪: 相手の退去要求に応じず、その場所に居座り続けた場合に成立します。
- 住居侵入罪: 正当な理由なく、相手の許可なく建物や敷地に立ち入った場合に成立します。
- 専門家の見解: 訪問による交渉は有効な手段ですが、あくまで相手の許可を得て行うべきです。退去を求められたら速やかに応じるのが鉄則です。
- 社会生活上の平穏を害する行為:
- NG行動: 昼夜を問わず、何度も電話をかけたり、FAXを送りつけたり、深夜に自宅に押しかけたりすること。
- 法的リスク:
- ストーカー規制法違反: 執拗なつきまとい行為とみなされる可能性があります。
- 違法な取り立て行為: 民事上の不法行為として、精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償を請求される可能性があります。
- 専門家の見解: 多くの企業は、電話連絡を午前9時~午後8時頃までに限定するなどのルールを定めています。連絡回数も過剰にならないよう注意が必要です。
1-2. 債務者の「プライバシー侵害」と「信用棄損」
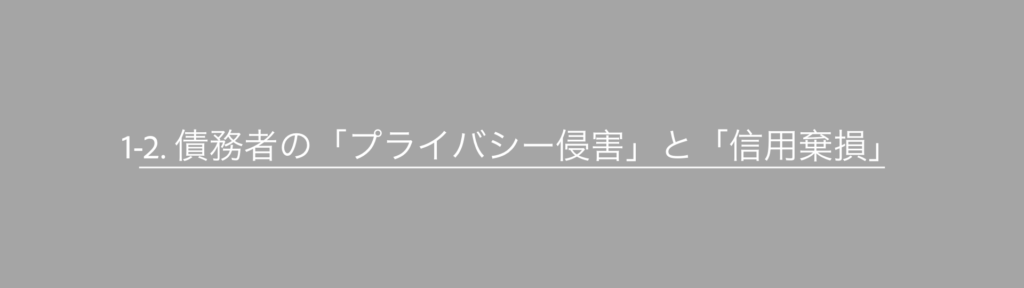
- 個人情報・プライバシーの侵害:
- NG行動: 債務者の家族や近隣住民、会社の上司や同僚に未払い金の事実をバラすこと。
- 法的リスク:
- プライバシー権の侵害: 債務者の個人的な情報を、本人の同意なく公開した場合に成立します。
- 名誉毀損罪: 公然と事実を摘示して他人の名誉を傷つけた場合に成立します。
- 信用毀損罪: 虚偽の風説を流布して他人の信用を傷つけた場合に成立します。
- 専門家の見解: 債権回収は、あくまで債務者本人との間の問題です。第三者を巻き込む行為は、すべて違法な取り立てとみなされます。
- 会社ウェブサイトやSNSでの非難:
- NG行動: 債務者の会社名や氏名を公表し、「未払い金を支払わない悪質な会社」といった非難の書き込みをすること。
- 法的リスク:
- 名誉毀損罪・信用毀損罪: インターネット上での書き込みは、一瞬で広がるため、より悪質と判断される可能性があります。
- 損害賠償請求: 書き込みによって相手の事業に損害が出た場合、多額の賠償を請求される可能性があります。
- 専門家の見解: 債務者への報復として書き込みをすることは、感情的で愚かな行為です。専門家に相談すれば、合法的な手段でより確実に債権を回収できます。
1-3. 弁護士法違反に繋がるNG行動
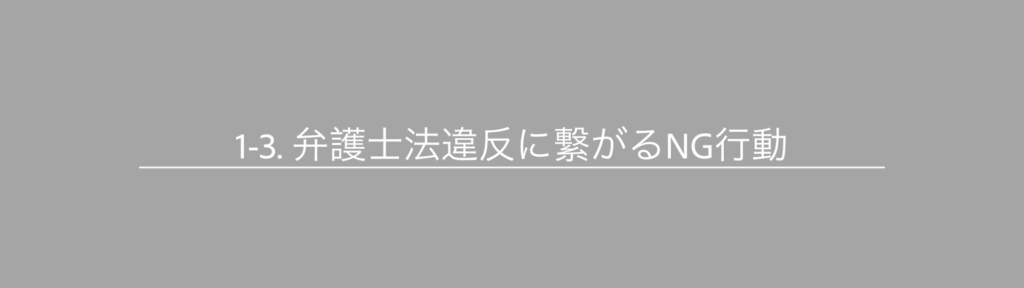
- 「弁護士」と偽る行為:
- NG行動: 自分が弁護士であると名乗って督促を行うこと。
- 法的リスク:
- 弁護士法第74条違反: 弁護士ではない者が、弁護士の肩書を使用してはいけないと定められています。
- 非弁活動:
- NG行動: 弁護士資格がないにもかかわらず、法律事務(交渉、訴訟など)を業として行うこと。
- 法的リスク:
- 弁護士法第72条違反: 法律で定められた弁護士以外の者が、報酬目的で法律事務を行うことを禁止しています。債権回収会社(サービサー)は、この法律の特例として認められた専門家です。
- 専門家の見解: 債権回収は「法律事務」にあたります。したがって、自社が回収する場合を除き、弁護士やサービサー以外の第三者に報酬を払って回収を代行させることは、違法となります。
表:債権回収におけるNG行動と法的リスクのまとめ
| NG行動 | 法律上のリスク(刑事罰) | 民事上のリスク(損害賠償) |
| 脅迫、暴言、暴力 | 恐喝罪、強要罪、暴行罪 | 不法行為による慰謝料請求 |
| 居座り、無断侵入 | 不退去罪、住居侵入罪 | 不法行為による慰謝料請求 |
| 夜間・過剰な電話 | ストーカー規制法違反(つきまとい) | 不法行為による慰謝料請求 |
| 家族や会社への暴露 | 名誉毀損罪、信用毀損罪、プライバシー権侵害 | 不法行為による慰謝料請求 |
| SNSでの非難 | 名誉毀損罪、信用毀損罪 | 不法行為による損害賠償請求 |
| 「弁護士」と偽る | 弁護士法違反 | (直接的な民事訴訟リスクは低い) |
| 弁護士資格なしでの回収代行(非弁活動) | 弁護士法違反 | (直接的な民事訴訟リスクは低い) |

第2章:回収を遠ざける「やってはいけない」心理的・事務的NG行動
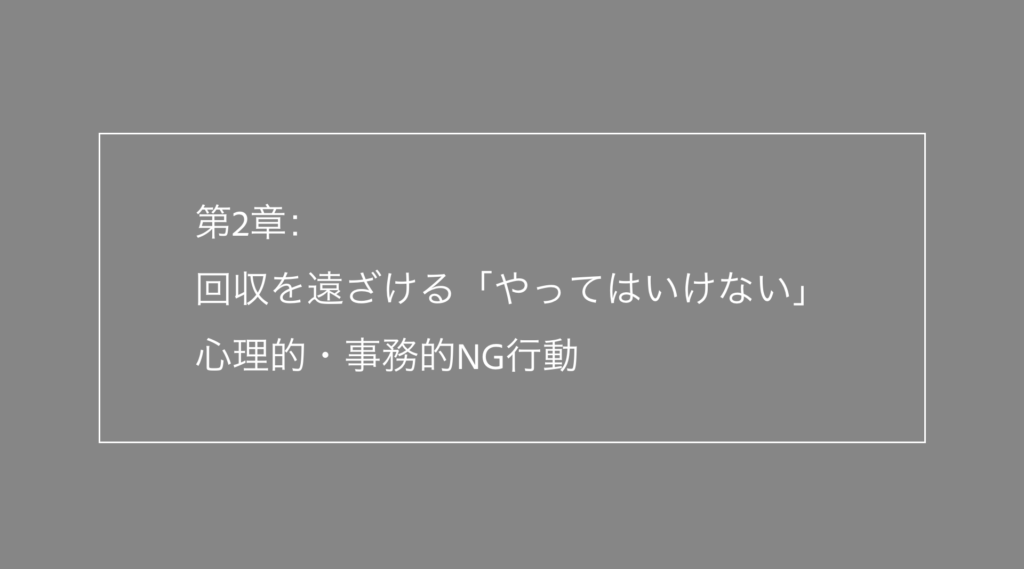
2-1. 心理的なNG行動:感情的な対応は百害あって一利なし
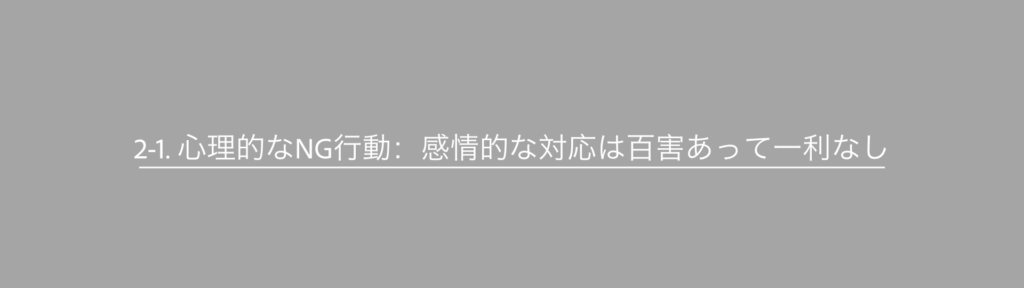
- 怒りや焦りを前面に出す:
- NG行動: 督促の電話やメールで、怒った口調や感情的な言葉を使うこと。「なぜ払わないんですか!」「もう待てません!」といった言葉は、債務者の反発を招き、話し合いを困難にします。
- 専門家の見解: 債権回収は、あくまでビジネス上の事務的な手続きです。感情的な対応は、債務者との交渉を感情的な対立に持ち込み、話し合いによる解決の道を閉ざします。冷静かつ事務的に、事実と要求を伝えることが重要です。
- 曖昧な要求・妥協:
- NG行動: 「いつか払ってくださいね」「そのうちでいいですよ」といった曖昧な要求をすること。また、「今回は半分でいいです」などと、簡単に妥協すること。
- 専門家の見解: 曖昧な対応は、債務者に対して「この会社は甘い」という認識を与え、支払いを後回しにさせる原因となります。具体的な支払い予定日や金額を明確に引き出し、約束を必ず書面で残すことが不可欠です。
- 諦めること:
- NG行動: 「どうせ払ってくれないだろう」と諦めて、督促を途中でやめてしまうこと。
- 専門家の見解: 債権回収は時間との勝負です。諦めて督促を止めると、債務者は支払う必要がないと判断し、他の債務の支払いを優先してしまいます。たとえ少額でも、最後まで諦めずに、段階的な督促を続けることが重要です。
- 謝罪から始める:
- NG行動: 「お支払いいただいていないようで、大変申し訳ありません」といった謝罪から入ること。
- 専門家の見解: 未払いは債務者側の問題であり、債権者側に非はありません。謝罪から始めると、債務者に「何か非があったのでは?」と勘違いさせ、不当なクレームを招く原因となることがあります。丁寧な言葉遣いを心がけつつも、毅然とした態度で臨むべきです。
2-2. 事務的なNG行動:小さなミスが大きな機会損失に繋がる
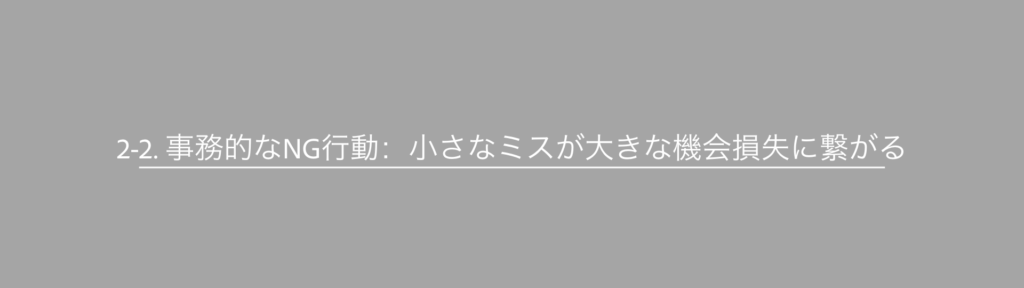
- 証拠の不備・管理不足:
- NG行動: 契約書がない、口約束のみ、請求書やメールの履歴を整理していない、通話記録がない、といった状態で督促や交渉を始めること。
- 専門家の見解: 債権回収の基本は「証拠」です。特に法的手続きに進む場合、客観的な証拠がなければ、債権の存在そのものを証明できません。すべての取引において、契約書、発注書、納品書、請求書、メールや通話記録など、関係書類を時系列で整理し、完璧に保管することが最も重要な予防策であり、成功の鍵となります。
- 債権情報・管理の属人化:
- NG行動: 未払い金の管理を特定の担当者一人に任せきりにすること。
- 専門家の見解: 担当者が不在になったり、退職したりすると、債権の状況が分からなくなり、回収が滞る原因となります。債権管理業務を標準化し、複数の担当者が情報を共有できる体制を構築しましょう。
- 初期対応の遅れ:
- NG行動: 支払期日を過ぎた後も、すぐに督促を行わず放置すること。
- 専門家の見解: 回収成功率は、未払い発覚後のスピードに比例して低下します。債務者から「この会社は督促が甘い」と見なされると、支払いの優先順位を下げられてしまいます。期日を1日でも過ぎたら、まず電話やメールで連絡するのが鉄則です。
- 督促手段の固定化:
- NG行動: 「電話」しか使わない、「メール」しか使わないなど、督促手段を限定してしまうこと。
- 専門家の見解: 債務者によっては、メールをほとんど見ない人もいれば、電話に出ない人もいます。電話→メール→書面→内容証明郵便→訪問など、段階的かつ多角的なアプローチで、債務者へのプレッシャーを徐々に高めていくことが効果的です。

第3章:NG行動を避けた上で、確実に回収するための正しいアプローチ
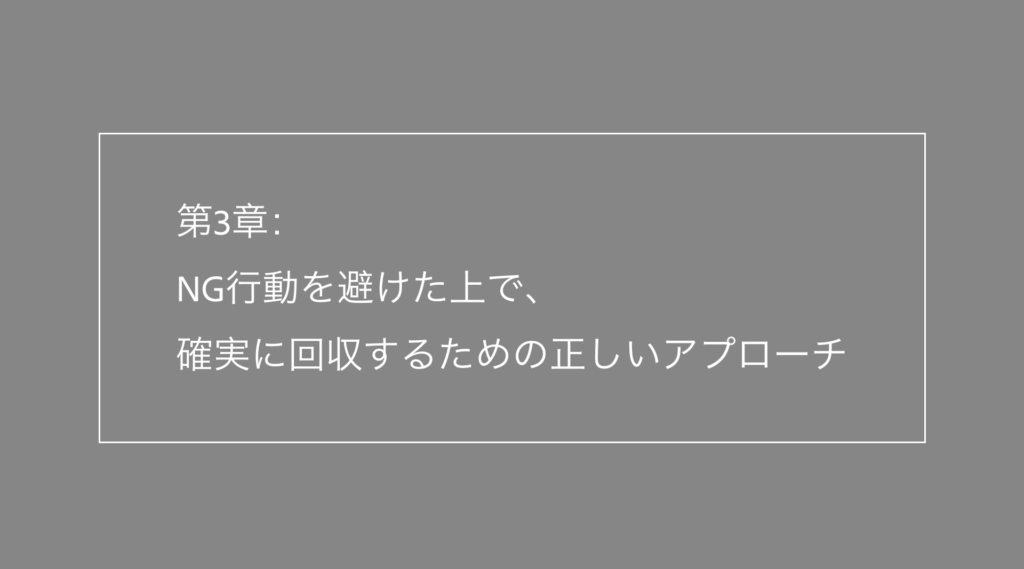
債権回収のプロは、上記のNG行動をすべて回避した上で、以下のような正しいプロセスに則って回収を進めます。
3-1. 自力回収での「正しい」行動プロセス
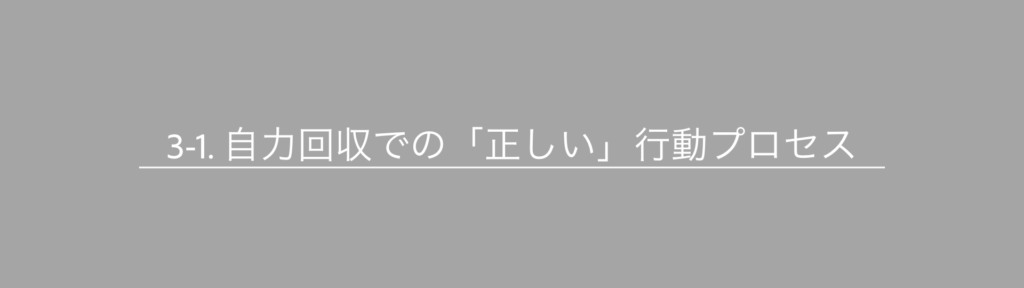
- ステップ1:未払い発生直後の「確認」
- 支払期日の翌日に、まずは経理担当者から債務者の担当者へ電話で連絡。
- 「お振込の確認が取れていないのですが、ご確認いただけますでしょうか」と、あくまで事務的な確認の体裁で、丁寧かつ冷静に事実を伝える。
- 債務者が「支払い済み」と主張した場合は、振込日時や振込名義、金融機関名などを確認する。
- 債務者が「支払っていない」と認めた場合は、理由と具体的な支払い予定日を聞き出す。
- ステップ2:未払い発生1週間〜1ヶ月後の「督促」
- ステップ1で解決しない場合、または支払い予定日を過ぎた場合、内容証明郵便の送付を検討。
- 宛先は法人の場合は代表者宛、個人の場合は本人宛とし、これまでの取引履歴、未払い金額、支払期日を明確に記載。
- 「本状到着後、〇日以内に支払いが確認できない場合は、やむを得ず法的手段を検討いたします」という文言を明確に記載する。これにより、債務者への心理的プレッシャーを高める。
- ステップ3:未払い発生2ヶ月後の「最終通告」
- 内容証明郵便で反応がない場合、債権回収の専門家への相談を検討する段階。
- 必要であれば、弁護士を介して再度内容証明郵便を送付。弁護士名義で送付されることで、債務者の心理的プレッシャーはさらに高まる。
3-2. 専門家へ依頼すべきタイミング
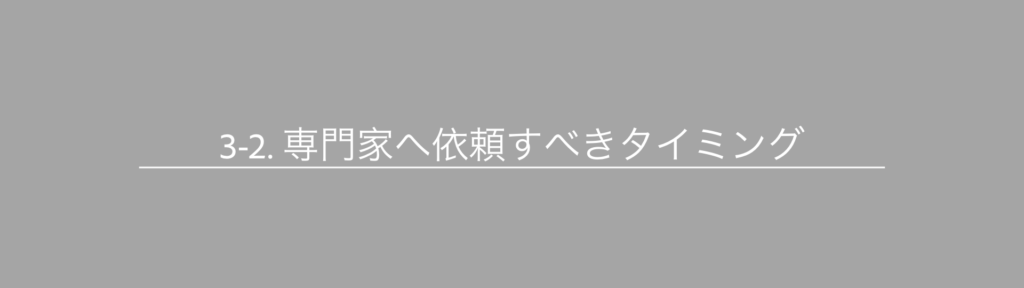
自力での督促や交渉に限界を感じたら、躊躇せず専門家へ依頼することが最善の選択です。
特に、以下の場合は専門家の介入が必須となります。
3-3. 債権回収のプロが絶対にやらないこと
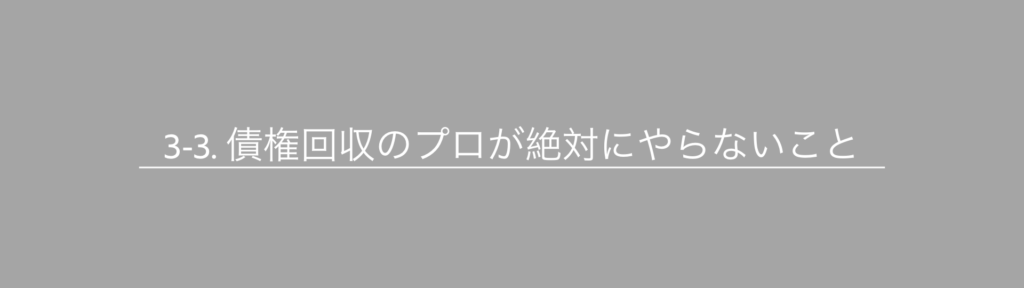
債権回収のプロである弁護士や債権回収会社は、上記のNG行動を絶対にしません。
彼らは、感情的なやり取りを一切せず、債務者の支払い意思や能力を冷静に見極め、最適な法的手段を講じてくれます。
彼らに依頼することは、違法な取り立てリスクを排除し、安全かつ確実にあなたの会社の正当な権利を守るための賢明な選択と言えます。

第4章:未払い金を「作らない」ための究極のリスクヘッジ
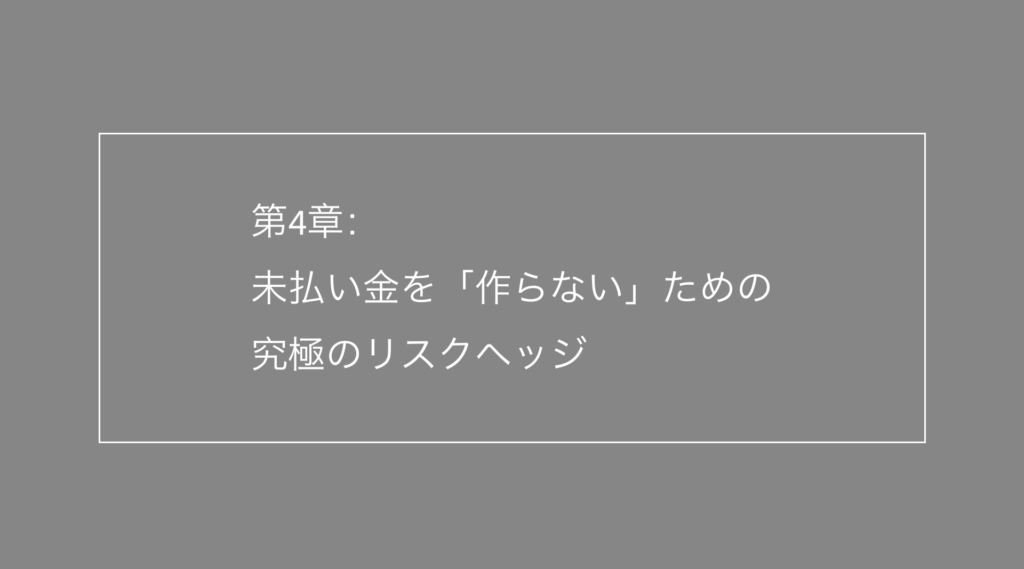
どんなに回収のノウハウを身につけても、未払い金が発生すれば、時間、労力、そして場合によっては専門家費用というコストが発生します。
- 与信管理体制の強化:
- 新規取引を開始する前に、必ず信用調査会社(帝国データバンク、東京商工リサーチなど)のレポートを取得し、取引先の財務状況や支払い能力を詳細に調査しましょう。
- 各取引先に対して、安全な売掛金の限度額を設定し、それを厳守することが重要です。
- 契約書の明確化:
- 全ての取引において、書面での契約を締結し、金額、期日、支払い方法、そして未払い時の対応を明確に記載しましょう。
- 請求・入金管理の厳格化:
- 請求書の発行と送付、入金確認をシステム化し、人為的なミスを防ぎましょう。
- 期日を過ぎた未払い金を自動で検知できる仕組みを構築し、初期対応の遅れを防ぎます。
その「万が一」に備える、最も有効で賢明なリスクヘッジこそが、売掛保証です。
取引先の倒産などにより、売掛金が回収不能になった際に、保証会社がその損失を補填してくれるサービスです。保険のようなイメージで、不測の事態からあなたの会社を守ります。
- 売掛保証のメリット:
- 貸し倒れ損失からの防御: 未払いが発生しても損失を補填してくれるため、キャッシュフローが安定し、黒字倒産のリスクを回避できます。
- 与信管理のサポート: 保証会社が取引先の与信審査を代行してくれるため、自社の与信管理業務の負担を軽減できます。
- 本業への集中: 未回収金の回収に時間や労力を割かれることなく、経営資源を本業に集中させることができます。

結論:NG行動を避け、予防と備えで未払いリスクをなくしましょう!
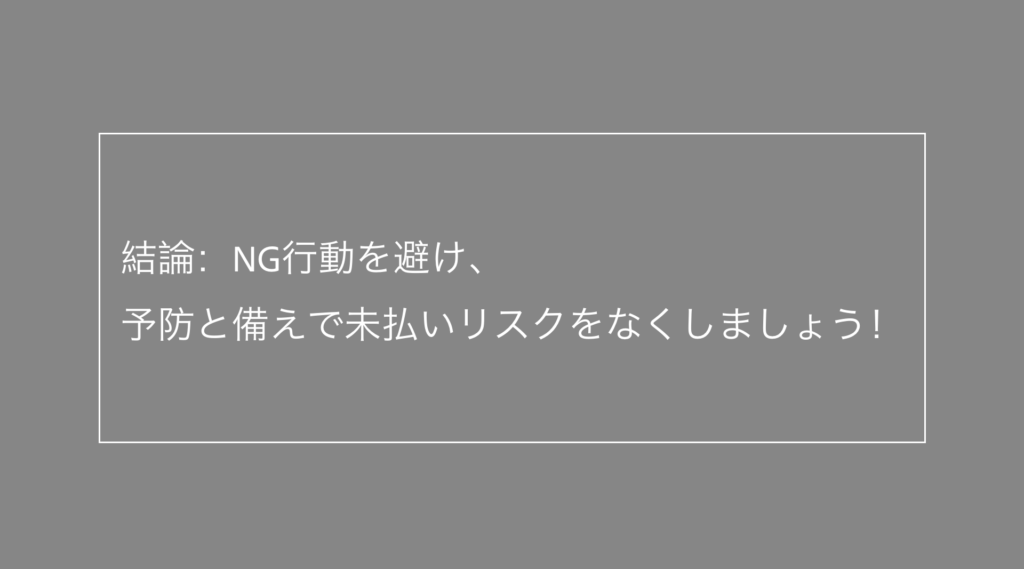
債権回収には、法的な知識と冷静さが不可欠です。
感情的な怒りや焦りに任せた行為は、すべてあなたの会社に跳ね返ってくることを忘れてはいけません。
本記事で解説したNG行動を絶対に避けた上で、自社での初期督促を徹底し、それでも解決しない場合は迷わず専門家の力を借りることが、安全かつ確実な回収への唯一の道です。
【補足:成功報酬で債権回収するならXP法律事務所とは】
XP法律事務所は、債権回収を成功報酬で行います。
ご興味ある方は下記から相談

債権回収に関してご相談
FAQ
①売掛保証・債権保証とは?
売掛保証とは、企業が商品やサービスを販売した際に発生する売掛金(未回収の代金)が、取引先の倒産や支払い遅延などで回収できなくなった場合に、保証会社や保険会社がその損失を補償してくれるサービスです。
これは、債権保証とも呼ばれ、企業の資金繰り安定や貸倒れリスクの軽減を目的としています。売掛保証を導入すれば、安心して新規取引や大口契約に挑戦でき、事業拡大を後押しする効果が期待できます。いわば、会社の売上を守る「安心の保険」のようなものです。
申し込みはこちら:https://toshika-lp.protocol.ooo/protocol-deal
②債権回収・未払い回収とは?
債権回収とは、企業や個人が、商品やサービスの提供、または貸付などによって発生した「債権」(お金を受け取る権利)について、約束の期日になっても相手方(債務者)から支払いがない場合に、そのお金を取り戻すための一連の活動を指します。
具体的には、支払いの催促(督促)、交渉、そして最終的には法的手段(内容証明郵便の送付、少額訴訟、通常訴訟、強制執行など)を通じて、未回収の資金を回収するプロセスです。会社の資金繰りを健全に保つ上で非常に重要な業務です。
申し込みはこちら:https://xp-law.com/saikennkaisyuu
